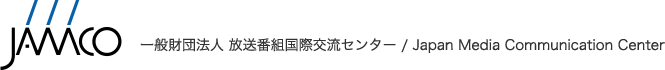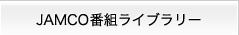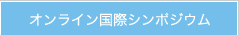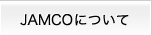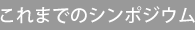第32回 JAMCOオンライン国際シンポジウム
2024年2月~
分断の危機にある世界で今訴えたいこと
他者理解へのパフォーマティブなアプローチ
越境的想像を通した多現実性への気づきに着目して
キーワード:他者理解,分断,越境的想像力,多現実性,パフォーマンス
1. はじめに:現実に対する正しい認識はあるのかー第一著者のパレスチナでの経験から
2019年9月,私は,パレスチナ暫定自治区ラマッラにある学校からの帰りの車の中で,一緒に移動していたパレスチナ自治政府教育省のスタッフが,その時SNSで話題になっていた動画を見せてくれた。その動画は,息子を殺されたパレスチナ人女性が,イスラエル兵にむけてナイフを振り回して叫んでいるところ,イスラエル兵がその女性を射殺する瞬間であった。イスラエル側は,これについて,凶器をもったパレスチナ人から身を守るために射殺したと説明したが,パレスチナ人たちはこの動画をみて「遠くでナイフを振り回す女性の何が危険なのか?銃を使わなくても女性から簡単にナイフを取り上げることができただろう」と発泡したイスラエル兵士を批判した。
他にもパレスチナーイスラエル間の衝突に関する多くの話を聞いた。たとえば,ラマッラ郊外の学校を訪問する道中,車窓から見える何もない土地は,かつてオリーブ畑だったそうだ。ある日,突然,イスラエル兵がセキュリティ上の問題として,パレスチナ農夫が育てていたオリーブの木を伐採してしまったこと,イスラエル兵が突然自宅にやってきて何かの容疑で息子たちを連行したこと(翌日には無罪として釈放された),学校のすぐそばにある入植地から催涙弾が飛んでくることがあるため学校では防災訓練が欠かせないこと,検問が突然はじまって学校に行けなくなる教職員や児童生徒がいるため毎日検問に関する状況把握が必要なことなどである。いずれも占領,テロ,分離壁,兵士,自爆,検問所を経験してきたパレスチナ人から聞いた話であり,長くパレスチナ側に身を置いて,見て,聞いて,感じた私の経験である。
私はパレスチナでの自分の経験を公に語ることはあまりない。その理由は,私の経験の多くが,パレスチナ人と近い位置から得たものだからである。私は,2002年から2011年までシリアのパレスチナ難民キャンプの教育開発に関わっていた。ユダヤ語は話さないがアラビア語は日常生活くらいにはできるし,パレスチナ自治区の学校の教育改善のために何度もパレスチナに渡航している。パレスチナのために何かしたいという気持ちが強く,また,私の身体性はパレスチナ人の感覚や思考の影響を多く受けているだろう。そのため,イスラエルーパレスチナを「正しく」「正確に」みることは難しいのである。
さらにいうなら,パレスチナ,イスラエルといった大きな主語でこの問題を語ることはできない。パレスチナ人にもイスラエル人にもいろんな考えや価値観の人がいて,彼らが経験している現実は多様である。壁の中で出会った幸せそうな家族,大親友なんだと1台の自転車を三人で交代しながら乗って遊ぶ子どもたち,目が見えなくても買い物ができるのよ,と買い物に一緒にいってくれた盲の少女,イスラエル兵と笑顔で挨拶をかわす青年,そこの住むひとり一人が経験する現実はちがう。もちろん占領下で多くのパレスチナ人が抑圧など似たような経験をしているが,周囲の人々や生活環境の違いによっても,人々が経験する現実は異なる。それは,イスラエル人に対しても同じことがいえる。
歴史的にも,政治的にも,文化的にも多様で複雑なイスラエルーパレスチナ間の問題に対して,ひとつの大きな主語(つまり,カテゴリー)で他者を理解するのではなく,一人ひとり違った人間として理解していこうと草の根レベルでの交流や対話の機会が多く作られてきた。しかし,大きな衝突が生じると,対イスラム,対ロシア,対パレスチナ,というように異質な他者をひとつのカテゴリーとして捉え,相手に対して警戒や嫌悪を高めていく。そのカテゴリーに含まれる一人ひとりには,その文化独特の共通の経験もあるだろうが,上述したように周囲の人々や生活環境の違いによって,人々の現実は異なるにもかかわらず,である。私たちは,受け入れ難い他者とどのように関わり,関係を築いていくことができるのだろうか。他者を「理解」するということはどういうことだろうか。
2.多文化主義思想の限界:他者を理解するだけで共生が実現するのか
著者らは,多文化共生に関心をもち,そのための方法を模索しながら研究をしている。日本では,1990年に出入国管理法の改正以降,在留外国人が増加し,その数は,2023年6月末時点で322万3,858人となった(法務省 2023)。多様な文化的背景を持つ人々と接する機会が増え,社会の多文化化にむけて,日本政府は「多文化共生」を掲げたが(総務省 2006),それを歓迎する声がある一方で,日本人と外国人の間でのすれ違いや衝突などの問題から,受け入れを歓迎しない声もある。そのような中,国や自治体(山脇・上野 2022),学校(恒吉・額賀 2021),地域団体(徳田ら 2019)は,多文化共生を推進するためのさまざまな取り組みを行っている。
多文化共生を推進する実践は必要不可欠であるが,その方法に対しては批判もある。日本人の多文化社会に対する意識に関する調査を行った永吉(2018)は,その批判の焦点を次の3つに整理して示した。ひとつは,多文化共生では文化的な権利の側面が強調されやすく,結果として経済的・社会的不平等が不可視化されていること,次に,文化的な異質性の強調は,「彼ら」と「われわれ」の分断を生んでいること。そして,食べ物や衣装,祭りなど文化を承認するコスメティック・カルチュラリズムにすぎず,表層的な理解にとどまっていることである。他者や異文化を「理解する」ことを中心とした実践に対して,永吉が示す批判は最もではあるが,実際には,他者や異文化を知ることは,相手の文化に関心を持ち,異なる言動について理解しようとし受け入れる動機にもなる。そして,知ることを通して,異なる信条や実践に対して嫌悪したり否認したりするのではなく,友好的,好意的である関係を構築する土台になることもある。ただし,『異文化間教育』の著者,アブダラ=プレッツェイユ(2021)も,文化の特徴を,独特な実態として捉えることに警鐘とならす。実際に私たちの日常生活には,物象化され,本質化された文化の概念が多く溢れている。西山が指摘するような「化石化や単純化」された文化や他者への理解はどのような問題を生じさせるのだろうか。
ひとつは,理解を中心とした実践だけでは,他者性を認めることができない現実を生み出すことである。ある日本人学生は,年配の方に電車で席をゆずろうとしたら,必要ないと強い口調で断わられ,なぜそんな言い方をされなければいけないのかと悲しさや怖さを感じたという。さらに,軽度の発達障害のある男性から,一方的に暴行を受けたと罵られた女性は,その男性の特性を知ってはいるがその言動をとても怖くて受け入れることができないと述べていた。理解を中心とした実践が成り立つのは,相手を理解できる,受け入れることができる限りであり,受け入れることができない他者や文化は排除されやすい。このように,多文化共生を推進する取り組みでは多様性を排除せず,受け入れる態度が推進されるが,実際には,その違いをただ受け入れることには限界がある。多文化共生における「寛容」の語りについて,ハージが考察したオーストラリアの事例について鈴木(2019)は次のように述べている。
排外主義的な暴動があった際,首相が「寛容に」と「国民」に呼びかける。その時呼びかけられている「国民」は,国籍の有無といった法的な意味における国民ではない。寛容にされる客体として暗黙の理に想定されているのは中東系やアジア系の意味であり,寛容にする主体として想定されているのはホワイトの人々である。ここでは法的な意味での「国民」/「移民」や皮膚の色という意味での「白人」かそれ以外といった区分ではなく,寛容にされるか否かを選択できない受け身的立場に立たされている「第三世界風にみえる人々」と自分にはかれらに「寛容」にするか否かを選択する権利があるのだと想像する「ホワイトの人々」という,想像上の人間の区分けが現実的な意味を持っている。(鈴木 2019, p.44)
これが示すことは,私たち(マジョリティ)の生活には,差異による「我慢」がいくつもあり,私たち(マジョリティ)は,それを我慢するかどうかを判断できるというわけである。つまり,我慢できない,受け入れられない,という選択肢がある。一方で,我慢される側(理解される側)には選択肢がない。この点に関して,著者らは,他者を認知的に「理解」すること,つまり,理解を中心とした多文化共生には限界があると考えた。
他者を理解する上で,カテゴリーは役に立つ。特に,受け入れ難い他者を理解する際,「自閉スペクトラムだから」「クルド人だから」「学生だから」「高齢者だから」「女性だから」というように,カテゴリーが参照される。理解しがたい他者について,その集団的傾向が分かれば,「だから,そうなのか」と納得し,わからない,という心理的負荷は軽減する。ニューマンとホルツマン(2020)は,そのように個人をカテゴリーでみることが社会で必要とされていることを認めつつも,カテゴリーから他者を理解することは,結果,他者を表面的にみていることにほかならないと指摘する。
現代社会は,人種,民族,宗教,セクシュアリティなどを含む様々な差異の状況だけでなく,あらゆるイデオロギーや政治的指向性が交差している。異なる信条や生き方をしている他者に対して,私たちはどのように向き合っていけば良いのだろうか。他者への「理解」を超えたアプローチがあるのだろうか。多文化主義が根ざす思考様式の限界をどのように乗り越えることができるのだろうか。
3. 理解から共感・変容へ
「寛容」を呼びかける構造は,結局は,同化主義と根本的に同じだとする鈴木(2019)の指摘をみてみよう。
主体のみに「寛容」を呼びかける構造がある限り,多文化主義的包含は同化主義的包含と同根である。なぜならこうした多文化主義は,つねにホワイトな主体から構成される社会空間を再生産しうる範囲内に限って他者を「寛容に」包含する,はじめから限界が設定された多元主義だからである。そこではホワイトな社会空間の構造倫理が前提とされ,それにかなう異質性のみが包含され,そうではない異質性は排斥される。(鈴木 2019 p.45)
これについて,鈴木は,ハージの概念である「多文化―同化主義装置」や「飼いならし」を用いて,「寛容」を呼びかける構造が,主体にとって脅威とならない他者のみを受け入れる(つまり,「飼いならし」状態の)多文化主義であると批判する。飼いならしの原義は,動物をしつけ,人間の必要性にそって利用できる家のものにすることであり,他者を「家」へ入れるためには,飼い慣らしが行われ,家を脅かす他者は排斥される。実際に,現代社会において,脅威となる他者を排斥しようとする動きが日々のニュースで流れている。本稿の最初に紹介したパレスチナーイスラエル問題はその顕著な事例である。主体が「居心地の良い場を維持する」ために,彼らを脅かす他者を排除しようとする行動ともいえる。
こうした多文化主義思考の中に,自分達の「居心地の良い場を維持する」ために,他者を利用しようとする飼いならしを見出したハージは,この問題を超えていくために,「私たち」と「彼ら」を線引きして,二元論的な見方をしている限り,差異に対して,肯定的な捉えかたはできないと指摘した。そこで彼が示したのが,他者を客体として見るのではなく,主体としてみることである。その具体的な方法を提案するにあたって,ハージは人類学の手法に着目した。
自己が生きる世界と根本的に異なる世界のありようを記述する人類学は,自己にとっては揺るぎない所与にみえる社会や存在のあり方を,異なる世界を知ることを通して相対化し,その再考を迫ってきた。そこでは別の世界のあり方を記述すること自体が,支配的とされた現実の見方や存在のあり方を揺るがすことで,ひとつの批判となりうるのだ(鈴木 2019, p.48)
人類学において,さまざまな存在のありようを現実に見出し記述する方法の基盤には「多現実論」がある。「多現実論」では,特定の人々やその社会,文化を固有のものとせず,存在を単一のあり方として捉えない。そうではなく,それぞれに応じた存在として捉えようとする見方である(鈴木 2019)。筆者らは,多文化主義が根ざす思考様式の限界を乗り越える手がかりを「多現実論」に見出した。「多現実論」には,身体を通して多元的な現実を経験できるという発想がある。
現実が身体に潜在する…可能性と現実界の存在的可能性との出会いだけとすれば,わたしたちが多元的な現実の内に住んでいると考えることは,人間身体がもつ潜在可能性の多元性を認識することである。それはつまり,身体がその環境と織り合わさる諸形態の多元性を認識することでもある。(Hage 2015, pp.68-69/鈴木 2019による訳)
「多現実論」では,さまざまな身体的関わりそれ自体が別個の現実を生み出すとする。先に紹介したパレスチナーイスラエルの事例もこの観点から説明することができる。どちらの主張が正しいのか,何が真実なのか,を議論の中心におくのではなく,それぞれがどのような現実を経験しているのかに着目する。つまり,何か唯一の客観的事実があり,その現実の見方が多様というわけではなく,同じ物理的空間にいたとしても,そこで経験される現実は,私たちの身体的差異によって異なるということを意味する。そして,私たちは,「他者」を自分の中に住まわせることで,多現実性を想像することはできる。
多現実性を想像するということは,「自分」の位置から「他者」を想像し,理解することではない。「他者」を自分の中に住まわせて,彼らの身体的位置から,その現実がどのように見え,そこで何を感じ,考えているのかを想像することである。塩原(2017)はこれを「越境的想像力」という概念で説明している。差異によって生み出された現実を,人々がどのように経験しているのかを想像していくことが,理解を中心とした他者理解とは違った,別のありかた(オルターナティブ)を生み出すことになる。別のあり方とは,ハージによると「私たちは何者であれ,個人そして社会として,いかなるときでも,いま,私たちが住まうのとは全く異なるありかたでこの世界に住むことができる」ということである。彼らが経験する現実を「想像」することができれば,他者の理解が,ただ違いを受け入れることではなくなるだろう。
4.いかに越境するのか:パフォーマンスへの着目
筆者らは多現実論に根ざした取り組みを考える上でパフォーマンスの実践に着目してきた。その際,前提としているのは,パフォーマンスは新しい自己を生成する場であり(Holzman 2016),他者との新しい関係性や世界での新しい住まい方を実験する場であるという考え方である。また,パフォーマンスの経験の中心にあるのは,動いたり,感じたりする「身体」である。そのため,パフォーマンスにおける自己のあり方や他者との関係性の探究は,必然的に身体を通して行われる。筆者らは,特に, 立場や経験などさまざまな点において,自分とは文化的背景が異なる「他者」になるというパフォーマンスに着目した。つまり,他者のことばやふるまいや態度などを模倣するパフォーマンスであり,それらのパフォーマンスを通して,他者との身体的な接近を経験することになる。
「他者」になりかわるパフォーマンスの実践は,これまでもロールプレイと呼ばれる教育方法として,学校や学校外教育プログラム,企業研修,セラピーなど,さまざまな現場で実施されてきた。その目的は,社会状況を理解したり,他者の立場を想像したり,その立場から何を感じるかを理解することが多い。その際,特定の問題や社会的状況に対して,正しい手順や理想的な状況に関する答えが用意されたうえで,適切に対処するための手続き上の知識を教えたりする。しかし,本稿における「他者」を自分の中に住まわせる活動は,最初から用意された正しい答えに導くためのものではなく,その中で,自己や関係性が構築されたり,脱構築されたりする,探究の場としてデザインされる。
この活動の特徴は,想像的で,空間を超えてさまざまな他者と関わりを持ちうることである。もうひとつの特徴は,この活動は,大抵観客の前で行われるため,1つの空間に,自分となりかわる「他者」と観客といういくつもの接点が複雑に交わり合うことから,その社会的プロセスは双方向的で,ダイナミックなものになることである。
そこで,本稿では,このようなパフォーマンスの実践において,どのような新しい自己や関係性が生成されるのか,どのように他者の現実を自分の中に見出したり,そのことでどのように他者との新たな関係が生まれたり,単一的な世界に住んでいた自己が解放されたりするのかについて,事例をあげて考察する。
5.活動の概要
本稿で取り上げるのは,明治大学国際日本学部の岸ゼミナール(岸ゼミ)での実践事例である。岸ゼミでは,アートベース・リサーチに取り組んでいる。そのひとつの活動である,異文化体験をテーマに演劇手法を取り入れた活動を取り上げる。
具体的な流れは次のとおりである。本活動は,ゼミの時間を3回(1コマ100分)使って実施した。第1回目では,学生は4−5人のグループになり,自分たちが経験した異文化体験,差別偏見の経験を共有した。その経験について深掘りするために聞き手は話し手に詳しく質問を投げかけた。そして,グループは,4−5の事例から関心をもったテーマを一つ取り上げ,その場面を実際に演じることになった。第2回目では,ドキュメンタリ演劇に関する萩原(2023)の文献を読み,日常の出来事をとりあげ,「日常の現実の再発見や再認識を促す」演劇の手法について理解を深めた。その後,グループのメンバーは,テーマについて経験をした学生に詳細な聞き取り調査を行い,自由フォーマットでシーンを作成した。そのプロセスで次々と新たな問いがうまれ,学生らはその場面を明確に想像できるように何度も質問をしながらシーンを完成させ,上演することになった。以下がそのひとつの事例である。
紹介するのは,「ビーガンの客が来たレストランでの異文化体験」をテーマとしたものである。登場人物は,店長,シェフ,ホールスタッフ(経験を語った学生),ビーガン客,その他の客である。シーンは, 新宿に位置する人気のパスタレストラン「SOU(仮名)」での出来事である。そこで働くナツ(仮名)は国際日本学部の学生アルバイトである。その日は特にお店が忙しい日曜日。そこに外国人観光客がやってきて「私はビーガンなのですが,ビーガンの料理はありますか?」と質問される。ナツは,店長にそれを伝えると,店長は「ほとんどのメニューに肉や魚が入っているけれど,これなら大丈夫だと思う」と限られたメニューを示す。客にそのメニューを伝えると「料理の際,お肉をつかったまな板や包丁は使わないでほしい」とさらにお願いされる。それについて,再び店長に伝えたところ「別にそれってばれなくない?」と言われる。
上演後,このシーンでの出来事について観客と対話した。他の4つの事例も同様の流れで行った。
6. 実践の結果と考察
学生の振り返り記録を分析した結果,経験からシーン作成へのプロセス,演じるプロセス,観客として経験するプロセス,観客と交流するプロセスに関して,それぞれに特有の学びがみられた。以下,「斜体」で示した部分は学生の振り返り記録を引用したものである。
- 6.1. 経験からシーン作成へのプロセス
学生たちは,その出来事が起こった状況を具体的に想像しながら,シーンを作成した。状況を明確に想像できない場合は,その出来事の経験者に質問をして,グループ全体でその状況を把握していった。「これはこういうことだったのかな? いや,こうも考えられるな,という隙が残っていたり,新たな問として課題が出されたりした方が,自分でもっとその題材について調べてみようという気持ちになったり,誰かに話してみようという気になります」という記述からもわかる。このやりとりを通して,当事者からの見えだけでなく,他の見え方にも気づいていった。
このように複数名でそのシーンを作成することで,シーンに登場する人々の言動についてあらゆる可能性を検討し,その場面がどのように構築されていたかに目を向けるようになった。「いつもの場面を取り上げて,演じることで,その時の情景や心情などを分析し,よりよくその現場をみることができる。たとえば,“なんか下に見られた感じがする”けれど,周りはそんなつもりはない。その場面を取り上げることで,何が,なぜ どんな場面でそう思わせるのかについて考えることができた」や「彼はその時どのような行動をとったのか,お客さんや店長は何と言っていたのかなど細かく皆で質問していって,状況を明確にしていきました。役のセリフを考える時,自分がその役になりきってみてその状況になった時なんと感じるのかを想像してみることで,心情や状況をより明確に感じることができました」といった記述からもわかるように,登場人物を描くプロセスをとおして,気持ちや状況にまで目を向けるようになっていた。 -
6.2.演じるプロセス
学生らは本番前に,何度か練習で演じながらシーンを作成していった。実際に他者になってみるという経験をすることで「やってみて自分たちが想定していなかったような気づきが得られて面白かったです」や「演じる,ということは,その演じる人物について深く知ることということである。その立場の人が持っている考え,実際の対応,発言,感じているジレンマなど,その人になりきって考えることができるので,より深く知ろうという気持ちになれた」というように,他者を客体としてではなく,自分の中に他者を住まわせ,その目線からその状況や感情を読み解こうとしていたことがわかる。
演じるというプロセスがあることによって,第1回目のセッションで行った異文化体験を共有した段階では見えてこなかった,登場人物の立場,ジレンマ,状況における思考,感情を感じとっていた。「実際に今回役を演じてみると,自分が体験したことがない経験を演じるだけで本当に体験したような気持ちになるし,演じることで異文化によって起こった問題をどのように解決したらよいかをより自分事として考えることができました」や「先生の経験談をもとに,先生の立場を演じてみた時。当時の先生の感情の細かな揺れ動きをより自分のものとして捉えることができました。演じるためには『その場面に置かれたらどんな行動を取るか?』,『どんな言葉を発するか?』をその対象に成り代わって考える必要があります。このプロセスがあるからこそ,自然と『自分ごとに置き換えて考える』といことができるのが演劇なのだと感じた」という記述が示すように,自分の中に他者を住まわせることで自分ごととして物事を考えるようになっていた。 -
6.3. 観客として経験するプロセス
発表の段階では,それぞれのグループがシーンを演じ,他のグループは観客として鑑賞した。どのグループも,上演を通して何を伝えたいのかは述べず,まずは,実際にそのシーンをみてもらってから「何が見えましたか,何を感じ,考えましたか」と観客に投げかけた。学生らは,観客として見ることの経験を通して,何が問題だったのか,なぜその問題が起こったのかなど,問題となる背景について,シーンにでてくるさまざまな登場人物に目を向けながら会話を始めた。たとえば「普通の飲食店でビーガン用の食事を求めるお客さんと,それに寄り添おうとする店員,そしてコストや他のお客さんのことを考えて行動しようとしていた店長がいましたが,誰も悪いわけではないと思いました」といった記述からもわかる。
また,「私は経験がない事例でしたが,会話をしているトーンは,日常の中でよく起こっていることなので,『そういう人いるよね』と共感できる部分が多くありました。友達と会話をしている中で,ちょっとした違和感をもってしまう場面や,傷つく場面があります。その人の価値観の中では,当たり前のことが,自分の中ではそうではない,またその逆もありえます」というようにシーンに出てくる登場人物の行動や感情が自分の経験とつながり,自分の経験について振り返るきっかけにもなっていた。 -
6.4. 観客との交流プロセス
演じた側は,観客との交流を通して,「劇をした人たちが考えていたこととは違った考えが観客から生まれた,という興味深い経験ができた」というように,新たな気づきを得ることができていた。演じる側も,取り上げた問題がなぜ起こったのかについて完全に理解できていたわけではない。グループでの事例の分析や議論を通してたどり着いた理解は,その段階ではまだ不完全なものである。しかし,「自分が差別かもと感じた状況も空気観や関係性が違ったら全く違うように受け止められる可能性があると知りました」や「1つの状況を見ていても受け取り方や見方,感じ方がこんなにも違うことを体感した。伝えたいことを表現して伝えるというのは言葉や行動をもってしても難しいことだけれど,受け取り方や考え方の違いを知る良い機会になりました」という記述からもわかるように,その不完全さを演じることを通して共有することで,また別の角度や立場からその状況について検討する機会を得ることができた。そうした経験を通して,学生は「自分だけのものさしで物事を見てしまうことの怖さを感じました。相手に寄り添うことが大切という意見が出ていましたが,相手に寄り添える範囲の限界はあると思います。自分の視野や思考に,そもそもないことには寄り添えないからです。そのため日頃から様々な事にアンテナを張って多様な見えを吸収していくことの大切さを学びました」と述べるように,多現実性に目を向けるようになっていた。
理解のプロセスを観客に開き対話をうみだしていくことは,従来の研究においてまさに課題であった点である。観客もまた,そのシーンを断片のまま見ることができるため,多様な物語(解釈)を紡ぎだすことができた。演じる側が見えていることも部分的であることから,観客はその見えを手助けすることができた。
本稿では,「他者」を自分の中に住まわせる活動を通して,ある一方の側の論理ではなく,その人自身の視点からの感じ方や見え方を理解しようと問い続けることによって,分からないながらも相手が置かれている状況や感情をイメージできるようになり,変化が起こっていることが示された。一方から他方への単なる理解ではなく,もうひとつの(オルターナティブな)見方が生まれてくることによって,受け入れられない他者は,不理解や攻撃の対象ではなくなっていく。
本稿で取り上げた事例は,自分の視点からは否定的に見えてしまう事象であり,相手の置かれている状況を描いていくプロセスで,その人がなぜそのような言動をしたのかについて,新たな視点で見つめ直すことができていた。そして,自分も同じ立場だったら「そうなるかもしれない」という感覚が芽生え,新たな側面での他者理解が生まれたと言える。
「他者」を自分の中に住まわせる活動は,当事者と全く同じ経験をしているわけではない。あくまでそれは,そうではないかという想像である。もちろん演じるプロセスにおいて,その場面でみられた言動について詳しくドキュメントしながら,シーンを構築するので全くのフィクションではないが,それでも,その時の感情や考えなどは,言動から想像した部分になる。また,相手がそういうふるまいをしたからといって,必ずしも同じ立場にたったとき,自分も同じような考え方やふるまい方をするわけでもない。ただ,もし自分がその人だったら,という観点から,その状況を想像することによって,自分もそうふるまう可能性があったかもしれない,と感じるものがあれば,そこに他者とつながりをもつことができると言えるのではないだろうか。
本活動の特徴は,最初から分かり合えない他者を想定した異文化体験を取り上げた。本活動を通して,学生らは,それまでとは違う感情や思考,行動と出会い,さまざまな他者と出会うことができた。異質な他者を自分の中に「住まわせる」ことは,自分自身の価値観や考え方が変化することではなく,そういう見方や感じ方もあるかもしれないという新たな視点を加えていくものである。
他者を自分の中に「住まわせる」ことは,他者を認知的に理解することとは違う。他者を理解し,受け入れようとする行為には,「飼い慣らし」が含まれることがある。一方,「住まわせる」活動は,他者を自分の一部として受け入れ,他者を客体ではなく主体として共に生きる場をつくる。そうすることで,他者を,理解する/受け入れる対象(客体)ではなく,自分の中に住む主体とすることで,私たちは,多現実性を生み出すことができるだろう。この観点では,他者は,不理解や攻撃の対象ではなく,共に生きる主体となる。
私たちにとって,他者を完全に理解し,受けとめることはなかなか難しい。これまでの異文化間教育や多文化教育では,他者を「理解」することを重視してきたが,本稿では,理解から,共感・変容につなげるためパフォーマティブなアプローチを試みた。相手への違和感を自分の評価基準で判断すべきではないことに気づくことで,他の基準があるのではないかと対話につないでいく。そのような対話ができることで,私たちは,他者とつながりをもち,関係性をつくることができるのではないだろうか。
謝辞
本実践研究を含め,アートベース・リサーチの探究を共にしてきた明治大学国際日本学部の岸ゼミナールのゼミ生に心から感謝しています。最高の知的パートナーとしての彼らのおかげで,多くの知と深い洞察を生み出すことができました。また,明治大学の萩原健教授,成城大学の青山征彦先生に,実践へのアドバイスをいただいたり,分析のプロセスで議論に加わっていただきました。心から感謝申し上げます。
参考文献
- フレド, ニューマン・ ロイス, ホルツマン (著), 茂呂雄二・岸磨貴子・北本遼太ら(訳)(2022)『パフォーマンス・アプローチ心理学—自然科学から心のアートへ』ひつじ書房 Lois Holzman(2016)Vygotsky at Work and Play, Routledge
- ハージ, ガッサン(著)塩原良和・川端浩平(監修)前川真裕子・稲津秀樹・高橋進之介(訳)(2022)『オルター・ポリティクス-批判的人類学とラディカルな想像力-』明石書店 Ghassan Hage(2015) Alter-Politics: Critical Anthropology and the Radical Imagination, Melbourne University Publishing
- 萩原健(2023)「研究の最前線<ドキュメンタリー演劇>と/の日常」『明治大学広報誌』, pp.34-35
- ロイス ホルツマン (著),茂呂 雄二 (翻訳)(2014) 『遊ぶヴィゴツキー: 生成の心理学へ』新曜社
- マルティーヌ, アブダラ=プレッツェイユ (著), 西山 教行 (訳)(2021)『異文化間教育』白水社
Maykel Verkuyten & Rachel Kollar(2021)Tolerance and intolerance: Cultural meanings and discursive usage. Culture & Psychology, Vol. 27(1) , pp.172-186
- 永吉 希久子(2018)「日本人の多文化社会に対する意識」『 東北文化研究室紀要』59,pp.35-47
- NHKニュース(2023) 米 パレスチナ系の学生銃撃事件 “ヘイトクライムの可能性” https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231127/k10014269961000.html(2023.12.1参照)
- 塩原良和(2017)『分断と対話の社会学:グローバル社会を生きるための想像力』慶應義塾大学出版会
- 塩原良和(2017)「越境的想像力に向けて」塩原良和・稲津秀樹編『社会的分断を越境する他者と出会いなおす想像力』青弓社, pp.25-49.
- 総務省(2006)『多文化共生の推進に関する研究会報告書』” https://www.soumu.go.jp/kokusai/pdf/sonota_b5.pdf(2023.12.1参照)
- 総務省(2023)『令和5年6月末現在における在留外国人数について』” https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00036.html(2023.12.1参照)
- 鈴木 赳生(2019)「多文化主義思想における他者性の否認―批判的人類学の挑戦に学ぶ― 『ソシオロジ』 63(3), pp. 41-58
- 徳田 剛・二階堂 裕子・魁生 由美子・武田 里子・高畑 幸・大森 典子ら(2019)『地方発 外国人住民との地域づくり―多文化共生の現場から』 晃洋書房
- 恒吉 僚子・額賀 美紗子(2021) 『新グローバル時代に挑む日本の教育―多文化社会を考える比較教育学の視座―』東京大学出版会
- 山脇 啓造・上野 貴彦(2022)『多様性×まちづくり インターカルチュラル・シティ―欧州・日本・韓国・豪州の実践から』明石書店
岸 磨貴子(明治大学) / 川島 裕子(関西大学)
岸 磨貴子
明治大学国際日本学部准教授。教育工学専門。研究テーマは「多様性をつなげる教育、多様性がつながる学習環境デザイン」。国内では、学校教育において総合的な学習の時間をはじめ「探究学習」を研究対象とし、インプロなどパフォーマンスを軸とした協働的な学びのための教育プログラムや教材を開発している。国外では、中東(シリア、パレスチナ、トルコ)を中心に、難民など社会的脆弱な立場におかれる子どもを含む誰もが個性や経験、強みなど多様性を発揮し共に発達していけるような場のデザインについての実践および研究を行なっている。
川島裕子
関西大学総合情報学部・准教授。トロント大学オンタリオ教育研究所博士課程修了(Ph.D.)。専門は教育学、コミュニケーション学、応用演劇。北海道教育大学にて、文部科学省経費による「教師に対する演劇的手法によるコミュニケーション教育」プロジェクトに従事したのち、初年次教育におけるコミュニケーション・プログラムおよび学校教育内外の多文化共生教育プログラムに関する実践研究に取り組む。身体性や実践知に重点をおいた演劇パフォーマンスを切り口に、ジェンダーや人種などの文化的越境や多層的自己を創出する教育プログラムを考究。アートベース・リサーチにも取り組む。著書に『〈教師〉になる劇場-演劇的手法による学びとコミュニケーションのデザイン』(編著、フィルムアート社、2017)、『街に出る劇場-社会的包摂活動としての演劇と教育』(共著、新曜社、2018)、『Arts-based method in education research in Japan』(共著, The Netherlands: Brill Sense, 2022)。論文に「Ethnicity as rigid boundaries and muted differences: Japanese youth experiences at school」(Educational Studies in Japan: International Yearbook, 13, 2019)ほか。