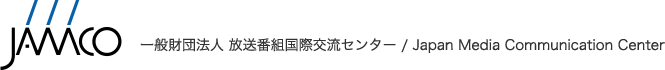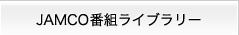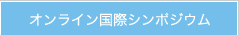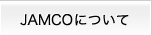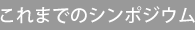第31回 JAMCOオンライン国際シンポジウム
2023年2月~2023年3月
世界的危機の中で「生きることの意味」を考える
外国人児童生徒にとっての日本の学校教育のアレンジメント
アクターネットワーク理論の視座からのシリア人の自己エスノグラフィーの分析
本稿では、外国人児童生徒が日本の学校教育においてどのような困難を経験し、それをいかに解決していったのかについて、当事者の一人である第二著者(ラーマ・ジャマル・アルディーン)Xの語りを手がかりに明らかにする。Xが直面した困難は、X個人の日本語力と日本に対する理解だけでなく、Xを取り巻く社会物質的な側面と複雑に関連している。本稿では、アクターネットワーク理論を視座とし、Xが直面した困難を、Xの自己の認識と社会物質的な側面とを関連づけながら第二著者(X)と第一著者の共同的、対話的な分析を通して考察する。
1.研究の背景
本研究の目的は、日本に生きるシリア人Xの自己エスノグラフィーを通して、来日後、日本の学校教育においてどのような困難を経験し、それをいかに解決していったのかを明らかにする。Xの困難は、社会物質的な側面と複雑に絡み合っている。そこで本研究では、日本に生きる第二著者Xが第一著者との対話を通して一人称の視点からその複雑性をそのまま描き、自己エスノグラフィーを執筆した。それをANTの視座から分析し、外国人児童生徒の学校教育における困難の発生とその状況について考察する。
3. 研究の方法
本研究の主なデータは、第二著者(ラーマ・ジャマル・アルディーン)Xの自己エスノグラフィーである。第一著者は、対話者としてXの自己エスノグラフィーに参加した。自己エスノグラフィーといえば、研究者本人による想起的な記述がその手法として広く知れ渡っていたが,沖潮(2013)は対話者を設定して、共同的に自己のライフストーリーを構築、分析・解釈する対話的な自己エスノグラフィーを実践している。沖潮(2013)はその意義として、他者の介在により新たな視点が生まれ,研究の拡がりが増す等の有用性があることを示している。
第一筆者がXと初めて出会ったのは、Xが高校生の時であった。その後、第一筆者が勤務する大学に進学したXとは現在に至るまで定期的にコミュニケーションを持っている。Xが自己エスノグラフィーに着手する前に、第一筆者は外国人児童生徒に関する先行研究に加えて、以下のデータを事前に収集した。ひとつは、Xが学校教育で担任の教師とやりとりしていた連絡帳である。そこには、Xの日々の経験が毎日記録されている。もうひとつは、Xのトークイベントの記録や難民としての自己について語った講演内容である。Xは日本で登録された数少ないシリア難民として、積極的に自己の経験を大学の授業やヒューマンライブラリーなどで共有をしている。その時に語った内容の記録やメモもデータとした。
対話的な自己エスノグラフィーに取り組むために最初に行ったのは、Xが来日してからのライフライン図の作成である。それを土台に、共同的かつ対話的に来日後から現在に至るまでの語りを構築していった。そのプロセスにおいて「当時私は、野良猫状態だった」「その時の自分は、学校に適応したいができずにもがく自分だった」という自己認識の表現が多くみられたことから、「◯◯な私」「△△な私」と自己認識をオーバーラップするものの、ひとつの区切りとして、第4節に示す8つの自己の観点からXが学校教育で直面した困難と解決を、それが発現するアレンジメントに着目して描いていく。
4. 日本という異国に生きる難民としてのXの自己エスノグラフィー
私はシリア出身のXである。Xは13歳の時に来日した。2011年にシリア危機が起こり、ダマスカスに住んでいたXの家族は、身の危険を感じ、国外に避難することを考えていたが、国外に避難するためにはお金がかかること、その道のりも非常に危険であったことから躊躇していた。しかし、2年後の2013年にシリア国内の状況はますます悪化し、終わりが見えない状態であったため、覚悟を決めて国外避難することにした。当初は、ヨーロッパをめざして移動を考えていたが、シリアから直接向かうことができなかったためエジプトに渡航し、それからスウェーデンに向かう予定を立てた。しかし、スウェーデン入国の許可が降りなかったことから、8ヶ月間エジプトで過ごした。その時、日本に長く住んでいた叔父にエジプトで再会でき、叔父の支援を受けて日本に入国した。
来日後、3ヶ月たった6年生の最後の2ヶ月半にあたる1月から3月の卒業式まで学校教育に行くことになった。シリア危機が起こってからも6年生の最初はシリアの学校に通っていたが、途中、通学が難しくなり通えなかったため日本で6年生最後から学校にいくことは、授業内容についていく点からも非常に困難を感じた。その後、地元の中学、高校へと進学し、UNHCRの支援を受けて大学へ進学し、現在にいたる。以下、Xが学校教育を受け始めてから、現在に至るまでのプロセスを「◯◯な私」の段階にわけて、Xが直面した課題とその解決について詳述する。なお、下線部はXが直面した困難、二重線は関連する社会物質的な側面を示している。
本研究では、日本に生きるシリア人Xとの対話的な自己エスノグラフィーの分析を通して、外国人児童生徒の一人であるXが日本の学校教育でどのような困難を経験し、それをいかに解決していったのかを、ANTを視座として、学校、日本語、日本社会、家族との関係などアレンジメントの変化に注目して検討してきた。
その結果、少なくとも次の3点について明らかになった。ひとつは、小学校から中学校は、日本語を覚え、日本社会を知る機会になっていたが、そのことが家族との関係を変え続けたことがわかる。日本語力と日本に対する理解が求められ、Xはそのプロセスでさまざまな困難に直面するが、支援団体から提供された教材や支援によってある程度これについて解決していった。一方で、Xの日本社会や学校への適応は、シリア社会の規範や価値の中にいた家族との間に境界を作ることになり、Xは問題解決のプロセスで新たな困難に直面し、複雑で、どうすればいいかわからないそんな葛藤状態の中生きていたことがわかった。
次に、高校では、自分と学校の間に積極的な意味が見いだせず、周囲とのつながりを感じられない時期であったことがわかる。日本語力と日本に対する理解の課題を克服したことで学業面ではうまくいき、通訳者として家族を支える立場になれたことによる達成感があるが、一方、学校では、日本人らしく、日本の学校に適応することが求められ、一方で、家庭ではそれまでの親子との関係ではない新たな関係をうまく構築することができなかったことから、自分の位置が見いだせなくなっていた。
3つめは、大学入学後、兄の存在や同じ関心や問題意識を持つ友達との出会い、そして自分の経験を捉え直す枠組みとなった学問は、Xが学校とのつながりを再構築する場となった。そこから自分と日本社会との関係も明確になっていった。このことは、X自身難民としての立場が大学の授業でうまく活かせたこととも関連している。
本稿では、Xをめぐる社会物質的側面によって、Xの直面する困難や問題解決がいかに発現していたのか、そして、Xのさまざまな人間性を表出することができた。Xの欲求や思い、意味、困難、問題解決の行為といった意志的行為(ANTにおいてこれをエージェンシーという)は、Xを取り巻くヒト、モノ、コトなど異種混淆な集合体の配置、編成に依存し、その変化によって変化している。Xが直面する問題はX個人の問題ではなく、家族や学校の他の児童生徒、支援団体や大学での友人、学問といったさまざまな社会物質的な側面と密接に関連しており、その社会物質的な側面もまたXによってさまざまに変化していることもわかった。
6. 課題と今後の展望
本研究では、第二著者の外国人児童生徒としての一人称の語りを手がかりに、ANTの視座から社会物質的側面との関係からその困難と解決がどのように起きたのかアレンジメントの観点から考察した。しかしながら、本研究におけるXの語りは「今は希望を持って生きている」立場からの回顧的な語りであり、これからのXの感情や関わりによって過去の経験は語り直され、それに伴い本研究では語られなかった社会物質的な側面も新たに見えてくるだろう。だからこそ、「いま、ここ」にいるXの語りを手がかりにすることに意義があり、また今後Xの語りに着目していくことで新たな展開が見られることが期待できる。
謝辞:本研究は、アクターネットワーク理論を専門とする成城大学社会イノベーション学部 心理社会学科教授 青山征彦先生に理論的な考察について助言をいただいた。感謝申し上げます。
参考文献
1.研究の背景
-
1.1. 学校における外国人生徒の現状と課題
日本国内の外国人児童生徒は、文部科学省(2019)によると、在籍者数は、平成30年度時点で小学校に約59,094人、中学校に約23,051人、義務教育学校に326人、高等学校に約9,614人、中等教育学校に151人、特別支援学校に約897人など、統計で約93,133人となっている。外国人児童生徒とは、成長・発達の過程で、文化や言語が異なる日本に移動し、生活し、学んでいる日本国籍を有していない学齢期にある児童生徒を示す。外国人児童生徒は、言語や文化だけでなく、文化的規範、集団の行動様式、価値観といった差異に直面する。これは外国人児童生徒に限ったことではなく、日本国籍を有する帰国児童生徒、サードカルチャーキッズ、国際児も同様である。外国人児童生徒等と「等」をつけるのはこのためである。
日本政府は、公立学校に就学する外国人児童生徒に対して、日本語指導などをはじめさまざまな支援を行っている。国籍に関係なく、全ての子どもには国連人権規約及び児童の権利に関する条約で学習権が保証されている。とはいうものの、2018年の文部科学省の調査では、日本語指導等特別な指導を受けている高校生の中退率は9.6%となり、言葉などの壁によって教育を受ける機会が奪われているという現状がある(文部科学省2021)。文部科学省は、2014年度から小中学校で日本語指導を「特別の教育課程」と位置づけ、授業として組み込めるようにした(佐久間 2014)。2023年度からは、高校でも日本語指導を、卒業単位として認定する方針を決め、国語に限らず高校の免許を持つ教員と、補助的に民間の日本語教師が教えられるようになる。日本語指導は外国人児童生徒が日本の学校に参画するための重要な要素ではあるが、問題は言葉だけではない。外国人児童生徒は、大人の都合によって移動を余儀なくされたこともあり、大人以上に葛藤を伴う。そのため、彼らのライフコースによりそった支援が求められる(齋藤 2012)。
外国人児童生徒の置かれている状況、ライフコースは多様である。そのため、その支援も多様となり、その地域や学校において具体的な支援の策定が求められる。学校では、外国人児童生徒の受け入れにあたって、保護者と子ども本人の面談を行い、必要に応じて日本語指導や適応支援を行う。自治体によっても対応はさまざまだが、通常学級に通ったり、巡回の日本語指導担当教員が支援にあたったり、各学校に配置された日本語指導教員が支援を行ったりするなどしている。また、障害のある外国人児童生徒は特別支援学級に在籍することになる。放課後には地域などのボランティアによる支援を行っている学校もある。
支援をすることだけでなく、何をどのように支援するかも重要である。基本的にこれらの支援の中心は、日本の学校への適応が優先される。そのため、たとえば、彼らの母語や母文化の学習は置き去りにされがちである(浜田 2022, Cummins 1996)。外国人児童生徒への支援を考える上で重要なことは、彼らの視点から学校教育での経験をとらえることである。たとえば、ニューカマーのブラジル人児童三人の学校適応に影響を与えた要因を調査した森田(2004)は、その重要性を示す事例を紹介している。森田によると、外国人児童らは普通学級では互恵的結合を通じて肯定的な自己意識を形成する一方で、日本人学級集団の主流派ではない周辺的な児童らとも自発的に連帯し助け合ったり、意識的に区別し離れたりすることでも肯定的な自己を模索していることを示した。この事例のように、外国人児童生徒の視点から学校教育での経験をとらえることで、彼らが一方的に文化を押し付けられられる受動的な存在ではなく、戦略をもって環境に働きかけるような独自の適応の在り方(岡村2022)を明らかにすることができる。 -
1.2. 外国人児童生徒の困難と解決の発現を捉える視座としてのアクターネットワーク理論
本研究では、アクターネットワーク理論(Actor Network Theory:以下 ANT)を理論的枠組みとする。ANTの視座では、さまざまな人、モノ、制度、道具などの構成要素をアクターとし、このアクターの配置、すなわち「アレンジメント」によって、各アクターの欲求や思い、意味、困難、問題解決の行為などが発現すると考える。外国人児童生徒のおかれている状況、ライフコースは多様である理由の一つは、その社会物質的な側面の多様性である。社会物質的な側面から外国人児童の学校教育での経験を分析することで、当事者である外国人児童生徒の欲求や思い、意味、困難や問題解決がどのようなアレンジメントの中で発現しているかを明らかにすることができる。
本研究では、当事者であるXの外国人児童生徒としての一人称の視点からの語りから、外国人児童生徒が直面する困難と解決が発現する学校教育のアレンジメントを探る。一人称の視点を含めることで、人間の社会物質的に位置付けられた自己と世界に対する理解を構築することができる(Schraube 2013)。外国人児童生徒が、学校教育におけるさまざまな人、モノ、制度、道具によって単に因果的に影響を受けているのではなく、それらと関わりながら行動しているエージェンティックな存在として描いていく。
本研究の目的は、日本に生きるシリア人Xの自己エスノグラフィーを通して、来日後、日本の学校教育においてどのような困難を経験し、それをいかに解決していったのかを明らかにする。Xの困難は、社会物質的な側面と複雑に絡み合っている。そこで本研究では、日本に生きる第二著者Xが第一著者との対話を通して一人称の視点からその複雑性をそのまま描き、自己エスノグラフィーを執筆した。それをANTの視座から分析し、外国人児童生徒の学校教育における困難の発生とその状況について考察する。
3. 研究の方法
本研究の主なデータは、第二著者(ラーマ・ジャマル・アルディーン)Xの自己エスノグラフィーである。第一著者は、対話者としてXの自己エスノグラフィーに参加した。自己エスノグラフィーといえば、研究者本人による想起的な記述がその手法として広く知れ渡っていたが,沖潮(2013)は対話者を設定して、共同的に自己のライフストーリーを構築、分析・解釈する対話的な自己エスノグラフィーを実践している。沖潮(2013)はその意義として、他者の介在により新たな視点が生まれ,研究の拡がりが増す等の有用性があることを示している。
第一筆者がXと初めて出会ったのは、Xが高校生の時であった。その後、第一筆者が勤務する大学に進学したXとは現在に至るまで定期的にコミュニケーションを持っている。Xが自己エスノグラフィーに着手する前に、第一筆者は外国人児童生徒に関する先行研究に加えて、以下のデータを事前に収集した。ひとつは、Xが学校教育で担任の教師とやりとりしていた連絡帳である。そこには、Xの日々の経験が毎日記録されている。もうひとつは、Xのトークイベントの記録や難民としての自己について語った講演内容である。Xは日本で登録された数少ないシリア難民として、積極的に自己の経験を大学の授業やヒューマンライブラリーなどで共有をしている。その時に語った内容の記録やメモもデータとした。
対話的な自己エスノグラフィーに取り組むために最初に行ったのは、Xが来日してからのライフライン図の作成である。それを土台に、共同的かつ対話的に来日後から現在に至るまでの語りを構築していった。そのプロセスにおいて「当時私は、野良猫状態だった」「その時の自分は、学校に適応したいができずにもがく自分だった」という自己認識の表現が多くみられたことから、「◯◯な私」「△△な私」と自己認識をオーバーラップするものの、ひとつの区切りとして、第4節に示す8つの自己の観点からXが学校教育で直面した困難と解決を、それが発現するアレンジメントに着目して描いていく。
4. 日本という異国に生きる難民としてのXの自己エスノグラフィー
私はシリア出身のXである。Xは13歳の時に来日した。2011年にシリア危機が起こり、ダマスカスに住んでいたXの家族は、身の危険を感じ、国外に避難することを考えていたが、国外に避難するためにはお金がかかること、その道のりも非常に危険であったことから躊躇していた。しかし、2年後の2013年にシリア国内の状況はますます悪化し、終わりが見えない状態であったため、覚悟を決めて国外避難することにした。当初は、ヨーロッパをめざして移動を考えていたが、シリアから直接向かうことができなかったためエジプトに渡航し、それからスウェーデンに向かう予定を立てた。しかし、スウェーデン入国の許可が降りなかったことから、8ヶ月間エジプトで過ごした。その時、日本に長く住んでいた叔父にエジプトで再会でき、叔父の支援を受けて日本に入国した。
来日後、3ヶ月たった6年生の最後の2ヶ月半にあたる1月から3月の卒業式まで学校教育に行くことになった。シリア危機が起こってからも6年生の最初はシリアの学校に通っていたが、途中、通学が難しくなり通えなかったため日本で6年生最後から学校にいくことは、授業内容についていく点からも非常に困難を感じた。その後、地元の中学、高校へと進学し、UNHCRの支援を受けて大学へ進学し、現在にいたる。以下、Xが学校教育を受け始めてから、現在に至るまでのプロセスを「◯◯な私」の段階にわけて、Xが直面した課題とその解決について詳述する。なお、下線部はXが直面した困難、二重線は関連する社会物質的な側面を示している。
-
4.1. 「野良猫状態」な私(小学生〜中学生1年生頃)
Xは、来日後1週間は、安心安全に暮らせる場所にたどり着いたという安心感でいっぱいになった。しかしながら1週間後その気持ちは大きく落ちた。というのは、ヨーロッパではすぐに難民認定がされるが日本ではそれがなかなか進まなかったからである。結局、来日してからしばらくは学校にも行けず、支援され続ける状態であったことから、Xは自分自身を「野良猫状態だった」と感じていた。来日して3ヶ月後、Xは学校教育(小学校)に通うことができるようになった。しかし、着の身着のままで来日し、難民認定申請中であったため家族は仕事もできず、貧困の中でのスタートだった。そのため、学校に同じ服を着ていくなどそういった外見から汚いといわれたり、教材やインターネットで学んだ日本語や日本のことを話すとバカにされたりするなどして辛い日々を送っていた。Xが通った学校にはX以外に外国人児童生徒は在籍しておらず、教師も子どもも英語が話せるわけでもなく、どう接すればいいかわからなかったかもしれない。しかし、Xからすれば、教師や周りの人に助けを求めても助けてもらえない、居場所がない、そんな状態に置かれていた。
-
4.2. 早く日本語を話せるようになりたいと必死になる私(中学1年生〜中学2年生)
そんな中、地域の外国人支援団体に行く機会があった。そこで、日本人スタッフやフランス人Yと出会う。彼らはボランティアで日本語学習支援を行っていた。Xはそこで日本語学習支援を受けながら、日常生活に必要な日本語を学ぶようになる。たとえば、挨拶、体調が悪い時の伝え方、トイレにいく時の許可の取り方、一緒に遊ぶ時の掛け声、「〜をください」や自己紹介の仕方など簡単な文型や単語である。外国人支援団体は、Xが日本語や日本文化を学ぶための冊子や教科書や学習機会を提供してくれた。Xは、それらの教材を使いながら自分で学んでいくようになった。また、いつもアラビアと日本語の辞書を持ち歩き、常に調べるようにしたり、友達や先生が話している単語を耳で聞き取り、知っているひらがなやカタカナでノートに書き、日本語の先生に見せて一緒に意味調べたりするなどした。このようにして、約8ヶ月後には、日本語で日常会話ができるようになった。さらに、フランス人Yは、Xが学校で経験している理解できない事象の理解を助けてくれた。たとえば、いわゆる「いじめ」を受けた時、最初はそれがいじめだとXは認識できなかった。なぜ、そんなことをされるのか、日本ではそれが普通なのかもしれない、とただ我慢するだけだったが、それが「いじめ」だということがわかり、学校の先生にSOSを求めることができるようになった。
4.3. 学校に適応したいがやりかたがわからない私(中学2年生〜中学3年生) -
4.4. 孤独の沼にいる私(中学1年生〜中学3年生)
6か月がたち、母と兄は就労ビザを取得して仕事をはじめた。Xの家族は、叔父の家を出て、部屋を借り、3人で暮らし始めた。自分達だけの生活のために必要なものを揃えたりするのはとても楽しかった。自分の居場所を作っていけると感じた。しかし、そうではなかった。母と兄は生活のために朝晩一生懸命働いていたので、家族とあまり会えなくなっていった。私は学校でなかなか馴染めずとても孤独を感じていた。しかし、母も兄も、学校や日本文化に馴染もうとしている私と家族の間で疎外感が生まれた。家族は日本の教育を受けたことがなかったので私が感じている困難が理解できなかったのである。私も家族が仕事で感じている辛さがわからなかったので、お互いがそれぞれ必死に生きていた。私は、家族ともあまり会えず、学校でも馴染めず、居場所がなくなり、孤独の沼にはまっていた。とはいえ、来日直後から通っていた外国人支援団体のスタッフさんやボランティアの方と頻繁に継続的に会うことができたことから、頑張り続けることができた。
4.5.家族の力になれる私(中学1年生最後〜高校3年生) -
4.6. 自分らしさをみつけたことで学校にいられなくなった私(中学校3年生の夏〜高校1年生)
Xは、通っていた外国人支援団体の紹介で、都内にある難民支援を専門に行う社会福祉法人とつながり、そこに通うようになった。そこでXは、学校とは違う環境の中で、学校でいるのとは違う自分と出会うことができた。その場所では、人はお互い気軽に声をかけたり、会話をしたりしていた。Xはそこでは、かつてのように明るい気持ちになり、よく笑った。自分が自分らしくいられると感じた。Xは学校での自分を「笑わない、暗い、猫背」とイメージしていた。しかし、自分は明るくて、ちゃんと笑えるんだと気づくことができた。その経験があったからか、学校教育に戻ることをこれまで以上に苦痛だと感じるようになった。Xは、学校に適応するために自分を消してきた、自分自信を否定したし、否定されてきた。日本人と同じように日本語ができるようになってきたことから、教師にSOSを出しても「みんなと同じ」「あなただけじゃない」と言われた。もちろん、教師はXが学校になじめるように常に力になろうとしてくれたが、それはXにとっては大きなプレッシャーとなることもあった。教師の気持ちもわかるが、それが自分にとって救いになることもあれば、負担になることもあり、その中で葛藤が大きくなった。また日常および学習で必要な日本語が十分にできるようになっていたことから、周りが自分について何を言っているのかがわかるようになり、日本語ができなかった時よりもずっと周りとの関係を作るのが難しいと感じるようになった。なぜこんなに苦しいのか、自分は何に悩んでいるのかそれがわからなかった。その状態を家族は理解できなかったため、気持ちが落ちてしまい、学校に行けなくなった時期もあった。一方で、学業面ではうまくいき、みるみると成績をあげることができた。
-
4.7.無難にやりすごす私(高校受験―大学進学前)
高校受験が終わり、新たな環境の中で心機一転した。Xはこの時には、人に迷惑をかけてはいけないと学習してきた。体調が悪くなると人に迷惑をかける、人に助けを求める時もそうだ。だからこそ、自分らしさを隠し通し、無感情で無難に日常を過ごすようになった。友達を積極的に作ろうと努力をすることもやめた。偏見をもたれたり、たった一度の失敗や行動でネガティブな印象を押し付けられたりしないように注意をした。目立つことをせず、ただ普通に過ごしていた。自分らしさを隠すことで自己肯定感は非常に低かった。しかしながら将来に期待はあった。大学生だった兄の話などからも、大学ではもっと自由に生きていけると想像していたからである。そのため、勉強だけに集中し、気持ちが少し楽になった。
-
4.8. 自分らしく生きられるようになる私(大学進学後―現在)
大学進学後では、Xは、自分自身の状態を客観的に見つめ直し、自分自身で問題解決の場を作れるようになった。自己肯定感をあげること、幸せの感情を取り戻すことを目標にし、兄と大学のカウンセラーの協力を得て、過去に自分に起こったことが現在の自分にどのように影響しているかを分析し、過去の経験をどのようにポジティブに活かせるかを考えた。そうするうちに、自分らしさというものを大学で少しずつ出せるようになった。大学3年生では、ゼミで多様性が発揮される学習環境デザインを学び、自分らしく振る舞える場について関心を持つようになった。それによって、自分らしさを出すことへの不安が減った。自分の経験を見つめ直すためのレンズとしての学問、何度も語り直せる場、多様性を重視し生かそうとするインクルーシブな学習環境、個性を発揮しやすい場があり、そういった場を自分自身が作り出せるということがわかり、今は希望を持って生きている。
日本語で日常会話ができるようになったとはいえ、日本の学校文化になかなか参画することができなかった。というのは、学級でどのように適切に振る舞えばいいかがわからなかったのだ。シリアでは当たり前だった習慣が、学校では受け入れられないということがあった。たとえば、舌打ちである。シリアでは簡単なNoに対して軽く舌打ちをする。「はさみ必要?」「舌打ち(いいえ)」というやりとりで使われる。学校で舌打ちをした時に周りを怒らせてしまったことがあった。Xは、自分の何がダメなのか、どこがだめなのか、なぜ注意されるのか、相手を怒らせてしまうのかわからなくなり、学校で毎日不安を感じていた。孤立を感じるようになり、なんとかクラス集団に入れるようになろうと、クラスで模範となる生徒の真似をして同じように振る舞おうとした。やればやるほど、自分でなくなる感覚になっていった。とても苦しいと感じた。しかし、先生や同級生に認めてもらえたら、疎外感を持たずに社会の一員になれると信じていた。だから正しく行動しようとした。しかし、いくら誰かの真似をしてもできるわけなく、日本人らしくしようとしても、結局自分は外国人なのだと感じ続けた。
日常生活レベルの日本語コミュニケーションができるようになり、家族のためにもできることが増えていった。Xが必死になってできるだけ早く日本語を習得しようとしたのは、自分の将来のためや友達を作るためだけではない。それに加えて、家族の負担を減らし、家族が日本で自立して生きていけるようになることだった。たとえば、市役所の手続きや病院の通訳などである。このようにXがアラビア語–日本語の通訳に関わり、家族の生活を支えるようになると、それまでの親子での関係性が変わり、Xが家族を支えていくという新たな関係になり、家族一人ひとりがそれぞれ戸惑いや葛藤を抱えるようになった。とはいうものの、家族が自分たちだけで生活できるようになることがXの目標であったため、それは達成されたことでXは安心感を得ることができた。
本研究では、日本に生きるシリア人Xとの対話的な自己エスノグラフィーの分析を通して、外国人児童生徒の一人であるXが日本の学校教育でどのような困難を経験し、それをいかに解決していったのかを、ANTを視座として、学校、日本語、日本社会、家族との関係などアレンジメントの変化に注目して検討してきた。
その結果、少なくとも次の3点について明らかになった。ひとつは、小学校から中学校は、日本語を覚え、日本社会を知る機会になっていたが、そのことが家族との関係を変え続けたことがわかる。日本語力と日本に対する理解が求められ、Xはそのプロセスでさまざまな困難に直面するが、支援団体から提供された教材や支援によってある程度これについて解決していった。一方で、Xの日本社会や学校への適応は、シリア社会の規範や価値の中にいた家族との間に境界を作ることになり、Xは問題解決のプロセスで新たな困難に直面し、複雑で、どうすればいいかわからないそんな葛藤状態の中生きていたことがわかった。
次に、高校では、自分と学校の間に積極的な意味が見いだせず、周囲とのつながりを感じられない時期であったことがわかる。日本語力と日本に対する理解の課題を克服したことで学業面ではうまくいき、通訳者として家族を支える立場になれたことによる達成感があるが、一方、学校では、日本人らしく、日本の学校に適応することが求められ、一方で、家庭ではそれまでの親子との関係ではない新たな関係をうまく構築することができなかったことから、自分の位置が見いだせなくなっていた。
3つめは、大学入学後、兄の存在や同じ関心や問題意識を持つ友達との出会い、そして自分の経験を捉え直す枠組みとなった学問は、Xが学校とのつながりを再構築する場となった。そこから自分と日本社会との関係も明確になっていった。このことは、X自身難民としての立場が大学の授業でうまく活かせたこととも関連している。
本稿では、Xをめぐる社会物質的側面によって、Xの直面する困難や問題解決がいかに発現していたのか、そして、Xのさまざまな人間性を表出することができた。Xの欲求や思い、意味、困難、問題解決の行為といった意志的行為(ANTにおいてこれをエージェンシーという)は、Xを取り巻くヒト、モノ、コトなど異種混淆な集合体の配置、編成に依存し、その変化によって変化している。Xが直面する問題はX個人の問題ではなく、家族や学校の他の児童生徒、支援団体や大学での友人、学問といったさまざまな社会物質的な側面と密接に関連しており、その社会物質的な側面もまたXによってさまざまに変化していることもわかった。
6. 課題と今後の展望
本研究では、第二著者の外国人児童生徒としての一人称の語りを手がかりに、ANTの視座から社会物質的側面との関係からその困難と解決がどのように起きたのかアレンジメントの観点から考察した。しかしながら、本研究におけるXの語りは「今は希望を持って生きている」立場からの回顧的な語りであり、これからのXの感情や関わりによって過去の経験は語り直され、それに伴い本研究では語られなかった社会物質的な側面も新たに見えてくるだろう。だからこそ、「いま、ここ」にいるXの語りを手がかりにすることに意義があり、また今後Xの語りに着目していくことで新たな展開が見られることが期待できる。
謝辞:本研究は、アクターネットワーク理論を専門とする成城大学社会イノベーション学部 心理社会学科教授 青山征彦先生に理論的な考察について助言をいただいた。感謝申し上げます。
参考文献
- Cummins,J.(2001)Negotiating identities:Education for empowerment in a diverse society,Ontario:California association for Bilingual Education
- 岡村佳代(2022)外国人児童生徒の異文化適応、異文化間教育学会(編著)異文化間教育事典, 明石書店, p.123
- 岸磨貴子(2019)学習環境としての分身型ロボットの活用-特別支援学校の生徒のパフォーマンスに着目して-, コンピュータ&エデュケーション, 46 巻 p.12-20
- 森田京子(2004)アイデンティティー・ポリティックスとサバイバル戦略 -在日ブラジル人児童のエスノグラフィー, 質的心理学研究, 3巻1号 p.6-27
- 齋藤ひろみ(2012) 外国人児童生徒のための支援ガイドブック―子どもたちのライフコースによりそって―,凡人社
- 佐久間孝正(2006)外国人の子どもの不就学−異文化に開かれた教育とは, 勁草書房
- 佐久間孝正(2014)文部科学省の外国人児童生徒受け入れ施策の変化, 専修人間科学論集第4巻2号 , pp.35-45
- 佐藤郡衛(2019)多文化社会に生きる子どもの教育−外国人の子ども、海外で学ぶ子どもの現状と課題, 明石書店
- 文部科学省(2019) 第1章 外国人児童生徒などの多様性への対応https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/22/1304738_003.pdf(2022年10月24日参照)
- 文部科学省(2021)外国人児童生徒等教育の現状と課題https://www.mext.go.jp/content/20210526-mxt_kyokoku-000015284_03.pdf(2022年10月24日参照)
- 沖潮(原田)満里子(2013)対話的な自己エスノグラフィ ―語り合いを通した新たな質的研究の試み. 質的心理学研究 第 12 号, pp.157-175
- Schraube, E. (2013) First-person perspective and sociomaterial decentering: Studying technology from the standpoint of the subject, Subjectivity, Vol.6(1), pp.12-32
- 山ノ内祐子・齋藤ひろみ(2016)第4章 外国人児童生徒の教育, 小島勝・白土悟・齋藤ひろみ(編)「異文化間に学ぶ「ひと」の教育, 異文化間教育学体系第一巻, 明石書店
岸 磨貴子 / ラーマ・ジャマル・アルディーン
明治大学 国際日本学部
岸 磨貴子(きし まきこ)
明治大学国際日本学部准教授。教育工学専門。研究テーマは「多様性をつなげる教育、多様性がつながる学習環境デザイン」。国内では、学校教育において総合的な学習の時間をはじめ「探究学習」を研究対象とし、インプロなどパフォーマンスを軸とした協働的な学びのための教育プログラムや教材を開発している。国外では、中東(シリア、パレスチナ、トルコ)を中心に、難民など社会的脆弱な立場におかれる子どもを含む誰もが個性や経験、強みなど多様性を発揮し共に発達していけるような場のデザインについての実践および研究を行なっている。
ラーマ・ジャマル・アルディーン
明治大学国際日本学部の学生。岸ゼミに所属し、「多様な社会的背景を持つ誰もが生きやすい場のデザイン」について実践と研究を行っている。学生として勉学に励む一方で、外国人児童生徒の学習支援などのボランティア活動を行っている。人や地域の多文化共生への理解促進のため、ヒューマンライブラリーや大学の講義、学校などで自らの経験を講演するなど積極的に取り組みを行っている。