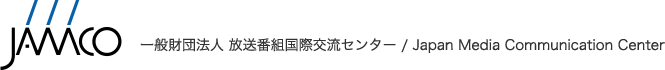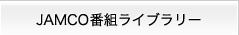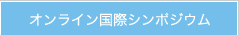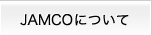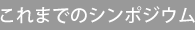第19回 JAMCOオンライン国際シンポジウム
2010年2月1日~2月28日
ドラマ映像の国際交流
日本のドラマが海外展開、国際交流に消極的だった構造的理由の考察
~日本特有の放送制度とその発展過程から~
1. はじめに
日本において、海外に向けて、自らのドラマを発信したいと考えているテレビ制作者は、過去も現在も残念ながら少数派である。但し、この数年でようやく少しずつではあるが、その傾向が崩れつつある。その背景には幾つかの要因がある。それを考えてみたい。ただ、その問題を掘り下げる為には、ドラマの国際交流というテーマから離れて、我が国のテレビが歩んできた特殊性から、話を進めていかなければならぬことをお許しいただきたい。
2. 日本のテレビ局をめぐる環境
日本のテレビドラマ関係者が海外展開を強く意識しなかった背景を考えるとき、まず、日本のテレビ業界が、正確にはテレビ局と言うべきかもしれないが創業以来、あまりに恵まれた経営環境にあったということがあげられるだろう。
1953年にNHKと民間放送第一号の日本テレビが開局しているが、それから56年、127社ある民間テレビ局は1社として倒産していない。日本国内にある様々な業界の中で、50年を超えて、市場から退場した企業が1社も存在しないというのは稀有の例であろう。
しかも、2007年度までの間、広告が事業収入の大半を占めるというビジネスモデルを変える必要に迫られる事もなく、常に売り上げは右肩上がりを続け、放送局の経営は景気の動向でその利益の伸びに影響が出る事はあっても、屋台骨を揺るがすような危機に見舞われることは無かったのである。
その、広告収入を左右する指標が視聴率である。従って、国内で高視聴率を獲得するドラマを制作するプロデューサーやディレクターは常に恵まれた制作費が保証され、自らが希望する番組企画を実現できる可能性も高まるという好条件の中で仕事を続けることを約束されていた。それが広告主のニーズとも合致していたからでもあった。
この環境の中では、海外で自分の作品を勝負してみたいとか、評価を仰ぎたいという意識を持つドラマ関係者はいないとはいわぬが、それほど切実に考える人間が多くないのは、さほど異常なことではないと思える。また、放送局もリスクを覚悟の上で経費をかけて、海外展開を積極的に行う必要性を感じていなかった。国際的な番組コンクールなどに出品するケースは少なくは無かったが、そこで評価を受けることによって、国内の広告主や視聴者に向けて自局の制作力をアピールすることに意義を感じていた。
その実績を海外での番組販売や国際交流に結びつけるという戦略は当初、ほとんど持つことはなく、期待もしていなかった。日本のテレビが国際的に商品として通用することはないと頑ななまでに信じこんでいる関係者は意外と多く、今でもそう考えている人間の方が多数派であろう。海外、特に欧米に売れる作品は芸術性を高く認められた単発ドラマというのが、日本国内における一般的見方である。その根拠として、言葉の壁。欧米とアジアの間に立ちはだかる超えがたい人種、文化の問題を指摘する関係者が多い。
3. 日本のドラマ制作をめぐる状況
海外の国際マーケットにテレビ局が積極的にブース展開するようになったのは皮肉なことに、テレビ局が映画作品を積極的に制作するようになってからであり、テレビドラマそのものの売り込みのために出展するようになったのは、つい数年前からである。
しかし、ここへ来て、新たな解決すべき問題が日本のドラマには生まれてきている。
ある時期までのテレビは、日本の家庭における家族共有の最大の娯楽がテレビ番組であっただけに、局側の番組編成や企画も、子供向けから老人ターゲット、そして家族全員が楽しめるものというように多様性があった。
この環境が維持されていれば、ドラマの制作者はクリエーターとして、自らの問題意識の中で個人としてのメッセージ性を内包した作品を世に問うという、多様多彩な作品がテレビを通して、発表されるという可能性が僅かながらも残されていたといえるかもしれない。
事実、ある時期までの日本のテレビ作品は、不振であった日本映画を凌駕する数々の名作や社会的にも影響力のある力作を残している。
勿論、現在でも、過去の作品に比べ遜色の無い名作、傑作があることは否定しないが、残念ながら総体から見れば、日本のテレビドラマが、傾向として、狭い領域にモチーフを求め、特定のターゲットに焦点を当てた作品が多く なり、どれもが似通った内容で、多種多様な広がりが無くなっていると言っても過言では無い状況に陥っていると思われる。
では、何故そうなったのであろうか、テレビ局の経営が曲がり角に来たことと最近のドラマ不振は無関係ではない。
メディアの広告効果がマーケット研究の進化とともに分析、分類方法が細部にまで検証可能となったことと、テレビを脅かす新たなメディアが続々登場したことで、その相互比較から、テレビを活用する広告手法はマスに商品の認知度を上げる利点はあるものの、その一方で商品説明能力には他媒体に劣後する面があると企業の広告宣伝担当者が強く認識するようになった。
その結果、経済成長が著しく、金銭的に余裕がある中で衝動的欲求に駆られてそれが消費行動に即、結びついたり、流行に乗り遅れたくないという国民意識が強い時代には、広告媒体として圧倒的優位性を示していたテレビのプレゼンスが、日本の経済力の衰退にメディア環境の激変も加わって、限定的な立場にと低下していった。
広告主のニーズが営業収益を左右する事業構造の中で、このような変化は当然放送局の営業担当者が番組編成にそのトレンドを考慮するよう要求する。営業要請を受けて、テレビ局の編成担当者は自局のタイムテーブルをそれに合わせて、大きく方向転換を始める。
その、方向性とは、解明されてきたテレビの広告媒体特性に敏感に反応する視聴者像、具体的には10代後半から30代前半の人々が好むであろう番組重視の編成にシフトすることである。
その結果、個人視聴率調査が導入された1990年代から、テレビ番組は業界用語でF1・M11 層と呼ばれている若い世代中心の内容の作品が民間放送の番組の圧倒的比率を占めるようになる。テレビドラマもその例外とはならない。
優秀な(放送局にとって有能なという意味だが)制作者ほど、そのニーズに沿った人気番組を作り上げる工夫をする。その結果、この10数年、NHKを除くと、大人(中高年者) が、見たいと思える番組が少なくなったと日本国内では盛んに言われるようになった。
実はこのことが、海外にも売れる番組を少なくすることにもつながっていく。
何故なら、国内で若者受けする番組を作る手短かな道は、人気アイドル、タレントを主役に据える事である。彼らは或いは彼女らは、(本人ではなくマネージメントをする芸能事務所はという方が正確)作品の質の高さより、役者本人の魅力を高めたり、引き出す内容を出演の条件とする。
少々、作品の内容や構成に無理があっても、主役が要求する設定やストーリーで脚本が作られ、企画力で勝負する時代から、人気タレントのブッキング能力を持つテレビ局やプロデューサーが競争の勝利者となる。
勿論、そのような作品であっても、ネットなどを通して、日本の芸能人に親しみを持ち、情報を得ている韓国、台湾など限定された東アジアの国においては、商品力を持つかもしれないが、およそ、日本のタレントの知名度が無い大半の国においては、何ゆえこのような企画の作品を自国で放送する意味があるのかと考えるのは当然である。
更に、それ以上に深刻な問題は、ドラマ制作に携わる、編成企画者、プロデューサー、ディレクター、脚本家の視点が常に、今の時期に国内で受ける作品は何かという一点に集中し、その時代の日本であるからこそ、通用するという一過性の作品が横行してしまうことにある。
このような、傾向が続く事は、ドラマ制作者の育成、教育にも悪影響が出てくるのは必然である。視聴率本位のものづくりに飽き足らず、本格的に人間をみつめ、社会問題を掘り下げて、そこから発表すべき作品を練り上げていくという、真の意味の作家性をもって、番組を通してメッセージを発信しようという気概を持つ人間は仕事の場を与えられる機会を失っていくケースが多い。
テレビドラマの将来に悲観し、その活動の場をテレビ以外に求めるようになり、去っていった制作者も多い。あたら有能な人材を失い、結果、時代や国境を越えて通用し評価される作品が作られる環境が破壊されてきたというのが、この20年近くの日本のドラマ現場の実態だったといえるのではないか。
4. 変わりつつある状況
ネガティブな実態の説明から入ったが、ここへきて、状況は変わりつつある。それは皮肉なことに、日本のテレビ局が持つビジネスモデルが崩れ、前年度でも、民放ネットワークのキー局《key局》として、番組の大半を系列局に制作、配信してきた東京の五局のうち三局が赤字決算となったことと大きく関わりがある。
もはや、広告収入に依存した経営では成長戦略が立てられないということから、民放キー局は放送事業外収入のシェアを伸ばし、多メディア時代に即した制作、企画能力を活用した事業分野へと、経営の優先度を高める方向に舵を大きく切ることによって事業構造の転換を図ろうとしている。
その結果、テレビ局である以前に、制作会社としての体質を強めていこうという姿勢が明確になってきた。
この事は、ここ数年の日本の映画の実績に顕著に表れている。長年に亘って、洋画が興行成績で圧倒的優位にあった日本の映画業界が、この数年間で邦画が洋画を上回り、ここ2年はその差を広げている。そしてその邦画のヒット作の大半はテレビ局が制作に関与しているのである。
最初のうちは、この理由はテレビ局が持つ自社媒体を使った広告宣伝力が観客動員に寄与している為といわれていたが、最近のヒット作はテレビ局自らが、企画しプロデューサー、監督を中心に制作スタッフの中核をも担うようになってきている。
このような、現象を何故、ここで論じなくてはならないかということについては、日本の放送界の発展形態の特殊性がある。
日本でテレビがスタートした当初、国内の映画業界はその創業以来最高の隆盛期にあった。当時は5つのメジャーな映画会社が存在した。後のテレビ局が、インターネットへのコンテンツ配信に一時、非協力的態度をとったこととも共通するのだが、この時代の映画会社もテレビを電気紙芝居と差別的言辞で誹謗するとともに、当時、映画会社専属制を取っていた俳優たちを映画5社で協定を結び出演させないことにした。
この為、テレビ局はスタート時から制作体制を自社内で整え、役者は映画業界以外から調達せざるを得ないという状況に追い込まれた。今となってはこの事が、テレビ局の発展にプラスに働く。俳優は芸達者でありながら経済的には恵まれていなかった演劇界の応援を受け、制作スタッフは当時の映画界に不満を感じて飛び出した人々を中心にすえ、若手新人教育も任せることになった。
欧米をはじめとして、アジアの諸国も含め、放送局と制作プロダクションは分離されているケースが主流である放送制作体制にあって、日本は50数年の歴史で、テレビ局が制作と放送を一元化して行う体制が、その間紆余曲折はあったものの維持されてきた。
ただ、正確に表現するなら、テレビ局は、たとえ制作プロダクションが実質的に作品を作っていても、自分たちが制作費を負担しているという理由から、著作権をプロダクションに部分的にしか与えない。或いは海外向けも含め番組販売窓口権を独占する形が慣例となっていた為、そのような状態が生まれたとの説明を付け加える必要があるだろう。
この問題は、長年に亘り、放送局と制作プロダクションの間で大きな係争状態を起こしてきているが、番組発注権を持つテレビ局側に強く逆らえる経済力と制作能力をもつ制作会社がごく少数しか存在しないことで、放送局有利の状態は変わらぬまま、現在に至っている。
もし、制作プロダクションが著作権や番組販売に関する権利を自分の意に沿う形で所有していれば、海外への番組販売や、海外との共同制作などは、現状以上に促進されていたのかもしれない。
欧米などから見れば、それでは映画会社は制作力があったはずなのに、テレビ局へのスタンスを草創期以降、テレビの社会的影響力が強まってから、変えることはしなかったのかという疑問が起きそうである。
しかし、日本においては、テレビの発展と反比例する形で映画会社はその制作力を落として行く過程を辿り、テレビ局は映画会社に作品を発注するより自社で制作したほうが視聴率も高く、クライアントニーズに応えやすいと判断し、単発の2時間ドラマを中心に制作依頼することはあっても、主流の連続ドラマは殆ど発注しなかった。
わずかに映画会社に依存したのは時代劇やアニメなどテレビ局がその制作構造上、手をつけにくい分野のみである。
ただ、ここで注目すべきことは、著作権が映画会社との契約においては、テレビ局にないため、アニメに関しては映画会社が積極的に海外などへのセールスに力を入れた。このことが、日本のアニメが世界の中で、大きなシェアを占めることに繋がっている。しかし、そこにもテレビ局とアニメ制作映画会社の特殊な商売上の関係が背景として存在する。
アニメは、日本が少子化時代を迎えるまでは、テレビにおいて高視聴率を稼ぐ筆頭ともいえるコンテンツであった。しかし、子供がターゲットということもあり、広告営業の面ではあまり歓迎される存在ではなかった。
この為、テレビ局は放映権のみを支払い、制作費は玩具やキャラクターの商品化権での商売を目論む広告代理店とおもちゃメーカーが、制作する映画会社とともに負担し捻出するという形が多くとられていた。このような、国内での放送だけでは費用を回収し辛いという環境が逆に海外に目を向けさせるという動きをよんだと思われる。国内の広告放送収入だけで充分な利益が生まれていたテレビ局が、あまり海外に目を向けようとしなかったことの逆証明がここにある。
少し角度を変えて、皮肉な見方をすれば、日本の放送業界、特に民間放送では企業経営の観点からは番組、作品を商品と見て、そこに付加価値を付けて販売するということは、あまり重要視されてこなかったといえるのかもしれない。利益を生み出す商売の源泉は視聴率に裏づけされた時間枠であった。
ある時間帯の視聴率を高くする為の素材が番組であり、ドラマなどの作品である。営業マンはあくまで、高い視聴率とその時間帯にテレビの前に釘付けにされているターゲットに合致した視聴者を売り物として顧客にセールスをしていたのである。無料広告放送2というビジネスモデルの本質をクールに捉えればそのように定義されるだろう。
その点、CATVが早くから発展し、国民の大半がCATVを通して、地上波も視聴するという、多チャンネルが当たり前のハードインフラの整備が進んだアメリカをはじめとする諸外国とはテレビ事業者やソフト制作者のあり方や発展過程も違っている。
日本でPAYTVの文化が定着するのは、わずか、10数年前からである。HBOやMTVのような地上波ネットワークを上回るソフト制作力を持つ事業者が、早くから日本に存在していれば、テレビ番組そのものの価値に対する考え方も大きく変わっていた筈で、その二次利用やコンテンツ流通の展開も違ったものとなっていたと思われる。
5. ドラマの国際交流
少々、虚無的な話になったが、ここからは、そのような前提に立ってドラマの国際交流、海外流通を考えたい。
ドラマに限らず、放送番組の国際交流、流通促進を考えるとき、二つの視点から見ていく必要がある。ひとつは「自国文化の海外発信とその結果生まれる国際間の相互理解」であり、第2点は「自国ソフトの海外販売という輸出産業としての貿易的側面」となる。
3年前の2007年秋に、日本では経済産業省が中心となり、映画、アニメ、ゲーム、キャラクター、劇画、音楽、ファッションそしてテレビ番組など様々な日本のコンテンツが相互に連携することなくバラバラに海外発信されていることの非効率を少しでも是正する意味で、毎年秋にそれぞれの業界が協力一体化して、日本のコンテンツの見本市とも言えるイベントを実施しようと「Japan国際コンテンツフェスティバル」を創設した。かねてより、実施されてきた『東京国際映画祭』『東京ゲームショー』『国際アニメフェア』の開催時期をある期間に集約して、海外からのバイヤーが集まりやすくするとともに、日本のソフトパワーを大いに喧伝しようという意図からの発想という方が分かりやすいかもしれない。
その一環として、『国際ドラマフェスティバルin TOKYO』もこの年からスタートしている。このイベントの目的は、「広告収入中心のビジネスモデルからの脱却を目指す民間放送と日本文化の国際的発信を国から強く要請されているNHKがお互いの垣根を取り払う努力をして協力関係を構築し日本のドラマの海外流通促進を計っていく」こと。更には、既に、ドラマの国際交流と自国のドラマの海外への発信の拠点となることを目的に設立されている中国の『上海テレビ祭』や韓国の『ソウルドラマアウォード』と連携友好関係を作り、東アジアのドラマが欧米、中東などにも市場競争力をつけることが出来るよう協力していこうというものであった。
私が、この『国際ドラマフェスティバル』の立ち上げから、第3回の今年までプロデューサーとして,業務に関わった立場から、具体的に感じたことを記述しておきたい。
日本のテレビ局が、海外流通に不熱心であったのは、上述した通りだが、それでも、20年以上前から、各民放局は国際部の中に、海外番組販売セクションを設け、細々ながらセールスを続けてきた。また、NHKは商社などと合弁でMICO(国際メディアコーポレーション)という番組販売会社をもち、積極的に海外へNHK中心の番組販売を続け、『おしん』などはアジア、欧米に留まらず、中東・アフリカでも放送されるという実績を残している。
ただ、このように地道な努力が続けられながら、日本の民放番組の海外への年間平均売り上げはここ数年100億円程度で、ドラマは其の内の30億円前後である。この理由として常に挙げられるのは日本とアジアなどの国とのあいだでの経済力の違いから生まれる『内外価格差』である。
具体的な事例で語ると、今、東京の某局と東南アジアの国との連続ドラマシリーズの価格交渉では1話当たり700USドルの差が埋まらず、交渉が頓挫しているという。日本側は自局の利益を最大限圧縮し、権利処理や必要経費で赤字にならぬ程度に販売価格を設定、買う側も会社として出しえる最高値を提示しても、この差が出てくるというのである。このシリーズは12本連続なので、売る側は8000ドル~9000ドル損をする計算になる。
ビジネスの観点から、このケースをみれば双方が如何に誠意を持って交渉しても、当分の年月、この問題は解決しないであろう。しかし、いずれアジアの国々の経済力が上がり、商談が成立する時期はやってくる。日本にとっても、今のうちに、これらの国々の市場に食い込んでおくことは将来の布石となるだけに目先の損得だけで考えるべきか、ということになる。
そのように考えたとき、国際交流、相互互恵の視点からも、今解決策を得られないものであろうか。答えはあるのではないか、と考えている。
『国際ドラマフェスティバル』は「東京ドラマアウォード」という国内外の作品を市場性、商業性を重視し顕彰するコンテストを併設している。勿論、クオリティも判断基準の対象になる。
この3年間で中国、韓国は当然の事としてベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア、インドなどの作品を表彰している。
その方式は各国のドラマコンクールやアウォードなどの実行委員会から優秀作品を3作品程度、推薦してもらい、日本側で独自に選考。日本の目から見た最優秀作を決め、スタッフ、キャストを招待、上映会と制作者の企画意図などを発表して貰っている。各国とも我々が考えていた以上の、実に高いレベルの作品なのである。
この上映会を観賞にきた、民放の複数の経営者がその出来の良さに驚きの声を上げていた。この経営者達は制作出身ではない。純粋に一視聴者として、面白いと感じたのであろう。と同時に、もっと制作能力は我が国と比べ劣ると考えていたのかもしれない。
このような機会を設けぬ限り、日本でアジアの連続ドラマを見る手立てはない。
更に、各国のドラマには、ドキュメンタリーとはまた違った意味でその国の世相や社会問題、宗教、文化が色濃く反映されているものだ。決して多いわけではないが、欧米、韓国、中国以外の作品を日本で放送することが年に各局で何本かはある。しかし、何故か、それは殆どがドキュメンタリーである。しかし、考えようによってはドラマの方がその国の実情や考え方、生活を色濃く反映しているケースが多いように思う。それも単発作品よりシリーズものの方がその傾向は強い。
地上波の深夜、BSなど、編成予算を多くもてずに苦労をしているところで、この『内外価格差』を利用することは出来るのではないか。アジアの連続ドラマを、積極的に買う事で、相手側にも日本のドラマを買う原資が出来るとしたら、交流は活発化するだろう。
いずれにしろ、我々がドラマの海外流通を促進させるにあたって、ただ、売ることだけを考えていたのでは、いずれ相手国の反発が生まれ、長い付き合いにはならない。売ろうとする以上は相手側の作品も積極的に買おうとする努力と国内の環境づくりに汗を流さねばならない。
「韓流」ブームはNHKのBSで火がついたが、もともとはCS放送のPAYTVチャンネルから秘かな人気が生まれている。いま、日本国内でも力をつけつつある中国ドラマ、『華流』もCSの中国語チャンネルから若者を中心に徐々に固定的なファン層が生まれつつある。いずれ、韓国ドラマと同等の人気を日本で得る時期が来るのではないか。
ただ、あえて我々の注文をさせてもらえば、これだけ日本で韓国作品が放送されながら、韓国のCATVでは認められても、地上波での日本作品の放送は、いまだ解禁されていない。歴史的な背景や国内のドラマ制作関係者の保護という理由は、十分承知した上で、少しずつ緩和政策をお願いしたい。中国にも、条件は違うが、相互互恵で番組交流がより緩和される事を将来的に考えてもらいたい。
何しろ、インターネットの普及は、現実的には作品の国際交流を活発化させ、海外作品の視聴に壁がなくなっている。
放送という領域で、様々なバリアーを作っても、既にそれは大きな効力を持たない。多チャンネル時代、作品視聴の選択を市民の判断に委ねる事が、国民相互の理解を深め、お互いが相手国を尊重する環境を生むものと考えたい。
国際的な枠組みでの共同制作や二国間の制作協力、あるいは、この3年間で視聴する機会のあったインドネシア、ベトナム、マレーシア或いは中東のテレビドラマに関しても私見を述べたかったが、紙面が尽きたのでここで、終わりとさせて頂く。
注
1. 業界用語でM1とは男性(M)の20歳から34歳まで、F1とは女性(F)の20歳から34歳までをさす。
2. 事業収入の大半を広告に依存して、その収入から制作費を捻出するというビジネスモデルで、視聴者は無料で視聴することができる。
日本において、海外に向けて、自らのドラマを発信したいと考えているテレビ制作者は、過去も現在も残念ながら少数派である。但し、この数年でようやく少しずつではあるが、その傾向が崩れつつある。その背景には幾つかの要因がある。それを考えてみたい。ただ、その問題を掘り下げる為には、ドラマの国際交流というテーマから離れて、我が国のテレビが歩んできた特殊性から、話を進めていかなければならぬことをお許しいただきたい。
2. 日本のテレビ局をめぐる環境
日本のテレビドラマ関係者が海外展開を強く意識しなかった背景を考えるとき、まず、日本のテレビ業界が、正確にはテレビ局と言うべきかもしれないが創業以来、あまりに恵まれた経営環境にあったということがあげられるだろう。
1953年にNHKと民間放送第一号の日本テレビが開局しているが、それから56年、127社ある民間テレビ局は1社として倒産していない。日本国内にある様々な業界の中で、50年を超えて、市場から退場した企業が1社も存在しないというのは稀有の例であろう。
しかも、2007年度までの間、広告が事業収入の大半を占めるというビジネスモデルを変える必要に迫られる事もなく、常に売り上げは右肩上がりを続け、放送局の経営は景気の動向でその利益の伸びに影響が出る事はあっても、屋台骨を揺るがすような危機に見舞われることは無かったのである。
その、広告収入を左右する指標が視聴率である。従って、国内で高視聴率を獲得するドラマを制作するプロデューサーやディレクターは常に恵まれた制作費が保証され、自らが希望する番組企画を実現できる可能性も高まるという好条件の中で仕事を続けることを約束されていた。それが広告主のニーズとも合致していたからでもあった。
この環境の中では、海外で自分の作品を勝負してみたいとか、評価を仰ぎたいという意識を持つドラマ関係者はいないとはいわぬが、それほど切実に考える人間が多くないのは、さほど異常なことではないと思える。また、放送局もリスクを覚悟の上で経費をかけて、海外展開を積極的に行う必要性を感じていなかった。国際的な番組コンクールなどに出品するケースは少なくは無かったが、そこで評価を受けることによって、国内の広告主や視聴者に向けて自局の制作力をアピールすることに意義を感じていた。
その実績を海外での番組販売や国際交流に結びつけるという戦略は当初、ほとんど持つことはなく、期待もしていなかった。日本のテレビが国際的に商品として通用することはないと頑ななまでに信じこんでいる関係者は意外と多く、今でもそう考えている人間の方が多数派であろう。海外、特に欧米に売れる作品は芸術性を高く認められた単発ドラマというのが、日本国内における一般的見方である。その根拠として、言葉の壁。欧米とアジアの間に立ちはだかる超えがたい人種、文化の問題を指摘する関係者が多い。
3. 日本のドラマ制作をめぐる状況
海外の国際マーケットにテレビ局が積極的にブース展開するようになったのは皮肉なことに、テレビ局が映画作品を積極的に制作するようになってからであり、テレビドラマそのものの売り込みのために出展するようになったのは、つい数年前からである。
しかし、ここへ来て、新たな解決すべき問題が日本のドラマには生まれてきている。
ある時期までのテレビは、日本の家庭における家族共有の最大の娯楽がテレビ番組であっただけに、局側の番組編成や企画も、子供向けから老人ターゲット、そして家族全員が楽しめるものというように多様性があった。
この環境が維持されていれば、ドラマの制作者はクリエーターとして、自らの問題意識の中で個人としてのメッセージ性を内包した作品を世に問うという、多様多彩な作品がテレビを通して、発表されるという可能性が僅かながらも残されていたといえるかもしれない。
事実、ある時期までの日本のテレビ作品は、不振であった日本映画を凌駕する数々の名作や社会的にも影響力のある力作を残している。
勿論、現在でも、過去の作品に比べ遜色の無い名作、傑作があることは否定しないが、残念ながら総体から見れば、日本のテレビドラマが、傾向として、狭い領域にモチーフを求め、特定のターゲットに焦点を当てた作品が多く なり、どれもが似通った内容で、多種多様な広がりが無くなっていると言っても過言では無い状況に陥っていると思われる。
では、何故そうなったのであろうか、テレビ局の経営が曲がり角に来たことと最近のドラマ不振は無関係ではない。
メディアの広告効果がマーケット研究の進化とともに分析、分類方法が細部にまで検証可能となったことと、テレビを脅かす新たなメディアが続々登場したことで、その相互比較から、テレビを活用する広告手法はマスに商品の認知度を上げる利点はあるものの、その一方で商品説明能力には他媒体に劣後する面があると企業の広告宣伝担当者が強く認識するようになった。
その結果、経済成長が著しく、金銭的に余裕がある中で衝動的欲求に駆られてそれが消費行動に即、結びついたり、流行に乗り遅れたくないという国民意識が強い時代には、広告媒体として圧倒的優位性を示していたテレビのプレゼンスが、日本の経済力の衰退にメディア環境の激変も加わって、限定的な立場にと低下していった。
広告主のニーズが営業収益を左右する事業構造の中で、このような変化は当然放送局の営業担当者が番組編成にそのトレンドを考慮するよう要求する。営業要請を受けて、テレビ局の編成担当者は自局のタイムテーブルをそれに合わせて、大きく方向転換を始める。
その、方向性とは、解明されてきたテレビの広告媒体特性に敏感に反応する視聴者像、具体的には10代後半から30代前半の人々が好むであろう番組重視の編成にシフトすることである。
その結果、個人視聴率調査が導入された1990年代から、テレビ番組は業界用語でF1・M11 層と呼ばれている若い世代中心の内容の作品が民間放送の番組の圧倒的比率を占めるようになる。テレビドラマもその例外とはならない。
優秀な(放送局にとって有能なという意味だが)制作者ほど、そのニーズに沿った人気番組を作り上げる工夫をする。その結果、この10数年、NHKを除くと、大人(中高年者) が、見たいと思える番組が少なくなったと日本国内では盛んに言われるようになった。
実はこのことが、海外にも売れる番組を少なくすることにもつながっていく。
何故なら、国内で若者受けする番組を作る手短かな道は、人気アイドル、タレントを主役に据える事である。彼らは或いは彼女らは、(本人ではなくマネージメントをする芸能事務所はという方が正確)作品の質の高さより、役者本人の魅力を高めたり、引き出す内容を出演の条件とする。
少々、作品の内容や構成に無理があっても、主役が要求する設定やストーリーで脚本が作られ、企画力で勝負する時代から、人気タレントのブッキング能力を持つテレビ局やプロデューサーが競争の勝利者となる。
勿論、そのような作品であっても、ネットなどを通して、日本の芸能人に親しみを持ち、情報を得ている韓国、台湾など限定された東アジアの国においては、商品力を持つかもしれないが、およそ、日本のタレントの知名度が無い大半の国においては、何ゆえこのような企画の作品を自国で放送する意味があるのかと考えるのは当然である。
更に、それ以上に深刻な問題は、ドラマ制作に携わる、編成企画者、プロデューサー、ディレクター、脚本家の視点が常に、今の時期に国内で受ける作品は何かという一点に集中し、その時代の日本であるからこそ、通用するという一過性の作品が横行してしまうことにある。
このような、傾向が続く事は、ドラマ制作者の育成、教育にも悪影響が出てくるのは必然である。視聴率本位のものづくりに飽き足らず、本格的に人間をみつめ、社会問題を掘り下げて、そこから発表すべき作品を練り上げていくという、真の意味の作家性をもって、番組を通してメッセージを発信しようという気概を持つ人間は仕事の場を与えられる機会を失っていくケースが多い。
テレビドラマの将来に悲観し、その活動の場をテレビ以外に求めるようになり、去っていった制作者も多い。あたら有能な人材を失い、結果、時代や国境を越えて通用し評価される作品が作られる環境が破壊されてきたというのが、この20年近くの日本のドラマ現場の実態だったといえるのではないか。
4. 変わりつつある状況
ネガティブな実態の説明から入ったが、ここへきて、状況は変わりつつある。それは皮肉なことに、日本のテレビ局が持つビジネスモデルが崩れ、前年度でも、民放ネットワークのキー局《key局》として、番組の大半を系列局に制作、配信してきた東京の五局のうち三局が赤字決算となったことと大きく関わりがある。
もはや、広告収入に依存した経営では成長戦略が立てられないということから、民放キー局は放送事業外収入のシェアを伸ばし、多メディア時代に即した制作、企画能力を活用した事業分野へと、経営の優先度を高める方向に舵を大きく切ることによって事業構造の転換を図ろうとしている。
その結果、テレビ局である以前に、制作会社としての体質を強めていこうという姿勢が明確になってきた。
この事は、ここ数年の日本の映画の実績に顕著に表れている。長年に亘って、洋画が興行成績で圧倒的優位にあった日本の映画業界が、この数年間で邦画が洋画を上回り、ここ2年はその差を広げている。そしてその邦画のヒット作の大半はテレビ局が制作に関与しているのである。
最初のうちは、この理由はテレビ局が持つ自社媒体を使った広告宣伝力が観客動員に寄与している為といわれていたが、最近のヒット作はテレビ局自らが、企画しプロデューサー、監督を中心に制作スタッフの中核をも担うようになってきている。
このような、現象を何故、ここで論じなくてはならないかということについては、日本の放送界の発展形態の特殊性がある。
日本でテレビがスタートした当初、国内の映画業界はその創業以来最高の隆盛期にあった。当時は5つのメジャーな映画会社が存在した。後のテレビ局が、インターネットへのコンテンツ配信に一時、非協力的態度をとったこととも共通するのだが、この時代の映画会社もテレビを電気紙芝居と差別的言辞で誹謗するとともに、当時、映画会社専属制を取っていた俳優たちを映画5社で協定を結び出演させないことにした。
この為、テレビ局はスタート時から制作体制を自社内で整え、役者は映画業界以外から調達せざるを得ないという状況に追い込まれた。今となってはこの事が、テレビ局の発展にプラスに働く。俳優は芸達者でありながら経済的には恵まれていなかった演劇界の応援を受け、制作スタッフは当時の映画界に不満を感じて飛び出した人々を中心にすえ、若手新人教育も任せることになった。
欧米をはじめとして、アジアの諸国も含め、放送局と制作プロダクションは分離されているケースが主流である放送制作体制にあって、日本は50数年の歴史で、テレビ局が制作と放送を一元化して行う体制が、その間紆余曲折はあったものの維持されてきた。
ただ、正確に表現するなら、テレビ局は、たとえ制作プロダクションが実質的に作品を作っていても、自分たちが制作費を負担しているという理由から、著作権をプロダクションに部分的にしか与えない。或いは海外向けも含め番組販売窓口権を独占する形が慣例となっていた為、そのような状態が生まれたとの説明を付け加える必要があるだろう。
この問題は、長年に亘り、放送局と制作プロダクションの間で大きな係争状態を起こしてきているが、番組発注権を持つテレビ局側に強く逆らえる経済力と制作能力をもつ制作会社がごく少数しか存在しないことで、放送局有利の状態は変わらぬまま、現在に至っている。
もし、制作プロダクションが著作権や番組販売に関する権利を自分の意に沿う形で所有していれば、海外への番組販売や、海外との共同制作などは、現状以上に促進されていたのかもしれない。
欧米などから見れば、それでは映画会社は制作力があったはずなのに、テレビ局へのスタンスを草創期以降、テレビの社会的影響力が強まってから、変えることはしなかったのかという疑問が起きそうである。
しかし、日本においては、テレビの発展と反比例する形で映画会社はその制作力を落として行く過程を辿り、テレビ局は映画会社に作品を発注するより自社で制作したほうが視聴率も高く、クライアントニーズに応えやすいと判断し、単発の2時間ドラマを中心に制作依頼することはあっても、主流の連続ドラマは殆ど発注しなかった。
わずかに映画会社に依存したのは時代劇やアニメなどテレビ局がその制作構造上、手をつけにくい分野のみである。
ただ、ここで注目すべきことは、著作権が映画会社との契約においては、テレビ局にないため、アニメに関しては映画会社が積極的に海外などへのセールスに力を入れた。このことが、日本のアニメが世界の中で、大きなシェアを占めることに繋がっている。しかし、そこにもテレビ局とアニメ制作映画会社の特殊な商売上の関係が背景として存在する。
アニメは、日本が少子化時代を迎えるまでは、テレビにおいて高視聴率を稼ぐ筆頭ともいえるコンテンツであった。しかし、子供がターゲットということもあり、広告営業の面ではあまり歓迎される存在ではなかった。
この為、テレビ局は放映権のみを支払い、制作費は玩具やキャラクターの商品化権での商売を目論む広告代理店とおもちゃメーカーが、制作する映画会社とともに負担し捻出するという形が多くとられていた。このような、国内での放送だけでは費用を回収し辛いという環境が逆に海外に目を向けさせるという動きをよんだと思われる。国内の広告放送収入だけで充分な利益が生まれていたテレビ局が、あまり海外に目を向けようとしなかったことの逆証明がここにある。
少し角度を変えて、皮肉な見方をすれば、日本の放送業界、特に民間放送では企業経営の観点からは番組、作品を商品と見て、そこに付加価値を付けて販売するということは、あまり重要視されてこなかったといえるのかもしれない。利益を生み出す商売の源泉は視聴率に裏づけされた時間枠であった。
ある時間帯の視聴率を高くする為の素材が番組であり、ドラマなどの作品である。営業マンはあくまで、高い視聴率とその時間帯にテレビの前に釘付けにされているターゲットに合致した視聴者を売り物として顧客にセールスをしていたのである。無料広告放送2というビジネスモデルの本質をクールに捉えればそのように定義されるだろう。
その点、CATVが早くから発展し、国民の大半がCATVを通して、地上波も視聴するという、多チャンネルが当たり前のハードインフラの整備が進んだアメリカをはじめとする諸外国とはテレビ事業者やソフト制作者のあり方や発展過程も違っている。
日本でPAYTVの文化が定着するのは、わずか、10数年前からである。HBOやMTVのような地上波ネットワークを上回るソフト制作力を持つ事業者が、早くから日本に存在していれば、テレビ番組そのものの価値に対する考え方も大きく変わっていた筈で、その二次利用やコンテンツ流通の展開も違ったものとなっていたと思われる。
5. ドラマの国際交流
少々、虚無的な話になったが、ここからは、そのような前提に立ってドラマの国際交流、海外流通を考えたい。
ドラマに限らず、放送番組の国際交流、流通促進を考えるとき、二つの視点から見ていく必要がある。ひとつは「自国文化の海外発信とその結果生まれる国際間の相互理解」であり、第2点は「自国ソフトの海外販売という輸出産業としての貿易的側面」となる。
3年前の2007年秋に、日本では経済産業省が中心となり、映画、アニメ、ゲーム、キャラクター、劇画、音楽、ファッションそしてテレビ番組など様々な日本のコンテンツが相互に連携することなくバラバラに海外発信されていることの非効率を少しでも是正する意味で、毎年秋にそれぞれの業界が協力一体化して、日本のコンテンツの見本市とも言えるイベントを実施しようと「Japan国際コンテンツフェスティバル」を創設した。かねてより、実施されてきた『東京国際映画祭』『東京ゲームショー』『国際アニメフェア』の開催時期をある期間に集約して、海外からのバイヤーが集まりやすくするとともに、日本のソフトパワーを大いに喧伝しようという意図からの発想という方が分かりやすいかもしれない。
その一環として、『国際ドラマフェスティバルin TOKYO』もこの年からスタートしている。このイベントの目的は、「広告収入中心のビジネスモデルからの脱却を目指す民間放送と日本文化の国際的発信を国から強く要請されているNHKがお互いの垣根を取り払う努力をして協力関係を構築し日本のドラマの海外流通促進を計っていく」こと。更には、既に、ドラマの国際交流と自国のドラマの海外への発信の拠点となることを目的に設立されている中国の『上海テレビ祭』や韓国の『ソウルドラマアウォード』と連携友好関係を作り、東アジアのドラマが欧米、中東などにも市場競争力をつけることが出来るよう協力していこうというものであった。
私が、この『国際ドラマフェスティバル』の立ち上げから、第3回の今年までプロデューサーとして,業務に関わった立場から、具体的に感じたことを記述しておきたい。
日本のテレビ局が、海外流通に不熱心であったのは、上述した通りだが、それでも、20年以上前から、各民放局は国際部の中に、海外番組販売セクションを設け、細々ながらセールスを続けてきた。また、NHKは商社などと合弁でMICO(国際メディアコーポレーション)という番組販売会社をもち、積極的に海外へNHK中心の番組販売を続け、『おしん』などはアジア、欧米に留まらず、中東・アフリカでも放送されるという実績を残している。
ただ、このように地道な努力が続けられながら、日本の民放番組の海外への年間平均売り上げはここ数年100億円程度で、ドラマは其の内の30億円前後である。この理由として常に挙げられるのは日本とアジアなどの国とのあいだでの経済力の違いから生まれる『内外価格差』である。
具体的な事例で語ると、今、東京の某局と東南アジアの国との連続ドラマシリーズの価格交渉では1話当たり700USドルの差が埋まらず、交渉が頓挫しているという。日本側は自局の利益を最大限圧縮し、権利処理や必要経費で赤字にならぬ程度に販売価格を設定、買う側も会社として出しえる最高値を提示しても、この差が出てくるというのである。このシリーズは12本連続なので、売る側は8000ドル~9000ドル損をする計算になる。
ビジネスの観点から、このケースをみれば双方が如何に誠意を持って交渉しても、当分の年月、この問題は解決しないであろう。しかし、いずれアジアの国々の経済力が上がり、商談が成立する時期はやってくる。日本にとっても、今のうちに、これらの国々の市場に食い込んでおくことは将来の布石となるだけに目先の損得だけで考えるべきか、ということになる。
そのように考えたとき、国際交流、相互互恵の視点からも、今解決策を得られないものであろうか。答えはあるのではないか、と考えている。
『国際ドラマフェスティバル』は「東京ドラマアウォード」という国内外の作品を市場性、商業性を重視し顕彰するコンテストを併設している。勿論、クオリティも判断基準の対象になる。
この3年間で中国、韓国は当然の事としてベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア、インドなどの作品を表彰している。
その方式は各国のドラマコンクールやアウォードなどの実行委員会から優秀作品を3作品程度、推薦してもらい、日本側で独自に選考。日本の目から見た最優秀作を決め、スタッフ、キャストを招待、上映会と制作者の企画意図などを発表して貰っている。各国とも我々が考えていた以上の、実に高いレベルの作品なのである。
この上映会を観賞にきた、民放の複数の経営者がその出来の良さに驚きの声を上げていた。この経営者達は制作出身ではない。純粋に一視聴者として、面白いと感じたのであろう。と同時に、もっと制作能力は我が国と比べ劣ると考えていたのかもしれない。
このような機会を設けぬ限り、日本でアジアの連続ドラマを見る手立てはない。
更に、各国のドラマには、ドキュメンタリーとはまた違った意味でその国の世相や社会問題、宗教、文化が色濃く反映されているものだ。決して多いわけではないが、欧米、韓国、中国以外の作品を日本で放送することが年に各局で何本かはある。しかし、何故か、それは殆どがドキュメンタリーである。しかし、考えようによってはドラマの方がその国の実情や考え方、生活を色濃く反映しているケースが多いように思う。それも単発作品よりシリーズものの方がその傾向は強い。
地上波の深夜、BSなど、編成予算を多くもてずに苦労をしているところで、この『内外価格差』を利用することは出来るのではないか。アジアの連続ドラマを、積極的に買う事で、相手側にも日本のドラマを買う原資が出来るとしたら、交流は活発化するだろう。
いずれにしろ、我々がドラマの海外流通を促進させるにあたって、ただ、売ることだけを考えていたのでは、いずれ相手国の反発が生まれ、長い付き合いにはならない。売ろうとする以上は相手側の作品も積極的に買おうとする努力と国内の環境づくりに汗を流さねばならない。
「韓流」ブームはNHKのBSで火がついたが、もともとはCS放送のPAYTVチャンネルから秘かな人気が生まれている。いま、日本国内でも力をつけつつある中国ドラマ、『華流』もCSの中国語チャンネルから若者を中心に徐々に固定的なファン層が生まれつつある。いずれ、韓国ドラマと同等の人気を日本で得る時期が来るのではないか。
ただ、あえて我々の注文をさせてもらえば、これだけ日本で韓国作品が放送されながら、韓国のCATVでは認められても、地上波での日本作品の放送は、いまだ解禁されていない。歴史的な背景や国内のドラマ制作関係者の保護という理由は、十分承知した上で、少しずつ緩和政策をお願いしたい。中国にも、条件は違うが、相互互恵で番組交流がより緩和される事を将来的に考えてもらいたい。
何しろ、インターネットの普及は、現実的には作品の国際交流を活発化させ、海外作品の視聴に壁がなくなっている。
放送という領域で、様々なバリアーを作っても、既にそれは大きな効力を持たない。多チャンネル時代、作品視聴の選択を市民の判断に委ねる事が、国民相互の理解を深め、お互いが相手国を尊重する環境を生むものと考えたい。
国際的な枠組みでの共同制作や二国間の制作協力、あるいは、この3年間で視聴する機会のあったインドネシア、ベトナム、マレーシア或いは中東のテレビドラマに関しても私見を述べたかったが、紙面が尽きたのでここで、終わりとさせて頂く。
注
1. 業界用語でM1とは男性(M)の20歳から34歳まで、F1とは女性(F)の20歳から34歳までをさす。
2. 事業収入の大半を広告に依存して、その収入から制作費を捻出するというビジネスモデルで、視聴者は無料で視聴することができる。
重村 一
ニッポン放送代表取締役 会長 日本映画テレビプロデューサー協会 副会長
早稲田大学、政治経済学部卒。 1968年フジテレビ入社、報道、編成企画を経て編成局長、取締役。 1997年スカイパーフェクトコミュニケーション(旧JskyB)転出、副社長、2002年代表取締役社長。 2006年~現職。その他、東映アニメーション取締役。